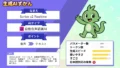今、日本ではクマが人里に降りてくるという深刻な問題が続いています。
では、世界ではどのような状況が起きているのでしょうか。
アメリカのカリフォルニア大学デービス校(UC Davis)の研究チームは、気候変動が野生動物と人間の関係にどのように影響しているのかを、大規模データを使用して詳しく調べました。
その結果、降水量が減少するごとに、野生動物とのトラブルが増加するという傾向が明らかになりました。
この研究成果は、2025年11月12日付の科学誌『Science Advances』 に掲載されました。
目次
- なぜ野生動物は人里に降りてトラブルを起こすのか?干ばつとの関係を分析
- 雨が減るほど野生動物とのトラブルは増える
なぜ野生動物は人里に降りてトラブルを起こすのか?干ばつとの関係を分析
野生動物が人里に降りてくる原因の1つとして、気候変動が挙げられます。
今回の研究の出発点となった疑問も、「気候変動で干ばつが増えると、人間と野生動物のトラブルは本当に増えるのか?もし増えるなら、どのくらいの影響があるのか?」というものでした。
世界各地で干ばつの長期化が進み、自然環境の水や植物が減少しています。
これにより野生動物が人の生活圏に近づくのではないかと指摘されてきましたが、その規模を定量的に示したデータはほとんどありませんでした。
そこで研究チームはまず、カリフォルニア州魚類野生生物局(CDFW)が運営する「Wildlife Incident Reporting(WIR)」データベースを分析しました。
このデータには、住民や職員から寄せられた野生動物とのトラブル報告が7年間(2017〜2023年)にわたり記録され、総数は3万件以上に達します。
報告内容は、家畜が襲われた、農地や庭が荒らされた、家屋が壊されたなどの「被害」と、ゴミをあさる・住宅周辺を徘徊するなどの「迷惑行動」が中心です。
なお、人身被害は別のデータとして扱われ、本研究の対象には含まれていません。
次に、研究者たちはカリフォルニア全域を50km×50kmのグリッドに区切り、各地域で「その時点から1年間の総降水量」を算出しました。
降水量が少ないほど、その地域で干ばつが深刻であると判断できる指標になります。
さらに、人口密度、樹木被覆率、世帯所得など、通報件数に影響すると考えられる要因も統計モデルに組み込みました。
これらの情報をもとに、研究チームは「干ばつ(降水量の減少)」と「野生動物とのトラブル」の関係を詳しく調べました。
対象となった動物は63種以上におよび、クマ、ピューマ、コヨーテ、ボブキャット、シカ、イノシシ、ビーバーなど多岐にわたります。
こうして、気候・人間活動・動物分布が複雑に絡み合う中で、干ばつが野生動物の行動をどう変えるかを、環境データと実際の通報データを組み合わせて明らかにしたのです。
雨が減るほど野生動物とのトラブルは増える
分析の結果、それぞれの区切りにおいて、年間降水量が1インチ減少するごと野生動物との“ネガティブな衝突”(トラブル)が2〜3%増えると分かりました。
年間降水量が1cm減少するごとに、野生動物との“ネガティブな衝突”が約1%前後増えるとも言えるでしょう。
さらに詳細を見ると、特に肉食動物で増加幅が大きいことがわかりました。
以下は、年間降水量が1インチ減少するごとの、野生動物によるトラブルの増加率(種別)を示したものです。
- ピューマ:2.11%増
- コヨーテ:2.21%増
- アメリカグマ:2.56%増
- ボブキャット:2.97%増
いずれも、干ばつによって餌となる草食動物の数や分布が変わりやすい種です。
干ばつで植物が枯れ、草食動物が減ると、それを追う肉食動物の行動域が広がり、人間の生活圏に侵入しやすくなります。
そして牧場の家畜、ゴミ、果樹、ペットフードなど、人間の資源が動物にとって“代わりの餌”として利用されてしまうのです。
また、季節の影響も見逃せません。
カリフォルニアでは5〜10月が乾燥期にあたり、動物とのトラブル報告が集中していました。
ここに“長期的な干ばつ”が重なることで、トラブルがさらに増幅される可能性が示されています。
興味深いことに、「単なる目撃」の数は干ばつと関係していませんでした。
これは、干ばつによって「動物を見る回数が増えた」というより、実際に迷惑や被害と感じる出来事が増えていることを示唆します。
ただし、この研究には限界もあります。
通報データは「人がどのような出来事を問題と感じるか」に左右されるため、干ばつで人がストレスを抱えやすい状況では、同じ行動でも“より深刻な問題として通報されやすくなる”可能性が残ります。
それでも、被害や迷惑行動だけが降水量と関連して増え、目撃だけは増えなかったという点から、研究チームは「心理的要因だけでは説明しきれない」と指摘しています。
研究の示唆は未来にも向けられています。
研究者たちは、「干ばつがトラブルを増やす仕組みがわかったなら、逆にそれを緩和する方法も作れるはずだ」と述べています。
その一例が、気候変動に強い自然環境の整備です。
自然の水源を守る、人里から離れた場所に動物が利用できる水場や植生を確保する、森林管理で動物の生息地を維持するなど、野生動物が人の生活圏まで来なくても生きていける環境づくりが重要だというのです。
今回の研究は、気候変動が私たちの庭先や街中での「野生動物との距離」すら変えてしまうことを示しています。
人間と野生動物の共存を実現するには、気候変動の影響を正しく理解し、自然環境を守る取り組みがこれまで以上に欠かせないものとなるでしょう。
参考文献
How Climate Change Brings Wildlife to the Yard
https://www.ucdavis.edu/climate/news/how-climate-change-brings-wildlife-yard
元論文
Human-wildlife conflict is amplified during periods of drought
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx0286#tab-contributors
ライター
矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。
編集者
ナゾロジー 編集部