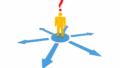肥満は健康にとって悪いもの、という認識は多くの人に浸透しています。高血圧や糖尿病、心臓病など、さまざまな生活習慣病のリスクが高まることは、よく知られています。
しかし実際には、肥満の人ほど認知症の発症率が低い傾向が、複数の大規模調査で報告されています。
この現象は「肥満のパラドックス」と呼ばれ、医学の現場でも注目されてきましたが、なぜこのような傾向が見られるのか、はっきりとした理由は分かっていません。
そこでアメリカのミネソタ大学公衆衛生学部(University of Minnesota School of Public Health)らの研究チームは、この疑問に対して5000人以上を対象に15年間追跡する大規模調査を行い、この「肥満のパラドックス」の背景に迫ろうとしました。
この研究の結果は、2025年5月に医学誌『Neurology』に発表されています。
目次
- なぜか「肥満」だと認知症が少ない
- 「肥満の“パラドックス”」実際は体重の安定が重要だった
なぜか「肥満」だと認知症が少ない
肥満は、高血圧や糖尿病、心臓病など多くの生活習慣病のリスクを高める要因として広く知られています。健康診断や医療現場でも、体格指数であるBMI(Body Mass Index:身長と体重から計算される値)が高いほど、将来的な病気のリスクが高まると繰り返し指摘されています。
たとえば、BMIが30を超える「肥満」の人は、正常体重の人と比べて糖尿病や心筋梗塞のリスクが2倍以上に高まるとする報告もあります。
しかし、認知症については少し違った傾向が報告されています。
「肥満の人ほど高齢になったときに認知症になりにくい」という傾向が、アメリカやヨーロッパ、アジアなど、様々な地域・人種を対象にした大規模研究から報告されているのです。
この奇妙な現象は「肥満のパラドックス(Obesity Paradox)」と呼ばれ、長いあいだ多くの研究者たちを悩ませてきました。
この現象の理由は明らかではなく、「なぜ他の生活習慣病と逆の結果が出るのか?」という疑問が長年にわたり議論されています。
しかし、この一見不可思議な現象については、調査上の見落としがありました。
これまでの多くの研究では、認知症を発症した後や診断時のBMIと、同じ年齢で認知症を発症していない人のBMIを比較して、両者の間にどんな違いがあるかという報告が行われていました。
しかし、認知症の発症が近づくと、発症の数年前から体重が減り始める場合が多いことがわかっています。そのため、認知症診断時のデータで比較すると、「認知症の患者には肥満の人が少ない」ことは当たり前であり、それが「肥満の人は認知症になりにくい」という誤認を生んでいる可能性があるのです。
つまり、実際には肥満であるかどうかが発症率に関連しているわけではなく、認知症発症の前兆として体重減少が起こっているだけかもしれないのです。
とはいえ、これまでのデータだけでは単に認知症に伴い痩せた人だけを見ていたのか、実際肥満の人には認知症発症率が低い傾向があるのかは、断定することが出来ません。
そこでミネソタ大学公衆衛生学部(University of Minnesota School of Public Health)を中心とする研究チームは、対象者の「BMI変化」に注目することにしました。
研究では5,129人を対象に、中年期(平均約60歳)から高齢期(75歳前後)まで、実に15年間にわたって追跡調査しました。
研究参加者の生活習慣や医療データをもとに、BMIの変化と認知症リスクとの関係を統計的に解析したのです。
この研究では、BMIがどのように変化したかを詳細に記録し、「高齢期のBMIが高い人」だけでなく、「中年期から高齢期にかけてBMIが減少した人」「BMIがほとんど変わらなかった人」など、さまざまなグループで比較を行いました。
さらに、認知症の診断には医師による詳細な面接や神経心理検査、医療記録など、多角的な方法が用いられ、信頼性の高いデータが集められています。
このように従来の研究の“穴”を埋め、「肥満のパラドックス」に本格的に迫った大規模調査を行ったのです。
「肥満の“パラドックス”」実際は体重の安定が重要だった
ミネソタ大学公衆衛生学部を中心とする今回の長期追跡によって、どのような人が認知症になりやすいのか、これまでにないほど詳細に分析することができました。
まず明らかになったのは、確かに「高齢期のBMIが高い、つまり肥満の人ほど、認知症のリスクが低かった」という点です。
BMIが標準体重(18.5〜24.9)と比べて、過体重(25.0〜29.9)の人は認知症リスクが14%低く、肥満(30.0以上)の人は19%もリスクが低いという結果が示されました。
この数字は、多くの人が持っている「肥満は健康の敵」というイメージとは反対の結果であり、「肥満のパラドックス」を裏付けるものです。
しかし、重要なのは「中年期から高齢期にかけてBMIがどのように変化したか」という問題です。
この点に着目すると、意外な事実が浮かび上がってきました。
中年期から高齢期にかけてBMIが大きく減少した人たちは、どのBMIグループであっても認知症リスクが大きく高まっていたのです。
たとえば、もともと標準体重だった人が高齢期にやせ細った場合、認知症リスクはおよそ2倍近くに跳ね上がりました。
一方で、長年にわたってBMIがほとんど変わらず、安定していた人ほど認知症リスクが最も低い、という結果も得られています。
このことは、「太っていること自体が認知症を防ぐ」のではなく、「高齢になって急にBMIが減ること」が認知症のサインかもしれない、という新しい視点をもたらします。
研究チームによれば、高齢期の急激なBMI減少は、健康状態の悪化や、食欲・活動量の低下、あるいは認知症のごく初期に見られる変化と関連している可能性があります。
つまり、BMIの減少が「病気の原因」ではなく「結果」であることも考えられます。
認知症のごく初期には、気づかないうちに食事量が減ったり、身体を動かすことが少なくなったりして、BMIが低下するケースが少なくありません。
この現象は「逆因果(reverse causation)」と呼ばれ、今回の研究結果を解釈する上で重要なポイントとなっています。
この研究の成果は、「BMIそのもの」よりも「BMIの変化」に注目することの大切さを教えてくれます。
特に高齢期に入ってから急にBMIが下がってきた、または食が細くなってきた場合には、それが健康のサインかもしれません。
自分自身だけでなく、身近な家族や高齢の親族のBMI変化にも気を配ることで、早めに異変に気づき、必要なケアや医療につなげることができるかもしれません。
今回の研究は、高齢期の肥満と認知症リスクの関係について新しい光を当てましたが、まだ多くの謎が残っています。
たとえば、BMI減少が「意図的なダイエット」なのか「病気や老化によるもの」なのかを区別することは、この研究ではできませんでした。
また、今回の参加者はアメリカの特定の地域に住む人たちであり、他の国や文化圏でも同じ傾向が見られるかどうかは今後の課題です。
こうした課題を乗り越えることで、「肥満のパラドックス」の正体にさらに迫ることができるでしょう。
「高齢期のBMI」と「認知症リスク」の関係には、まだ解き明かされていない部分が多くあります。
しかし、今回の研究は、「太っていること自体を無理に否定する必要はなく、むしろ体重が安定していることに注意を払うことが大切」という新しい視点を示しました。
日々の健康観察や家族のケアの参考に、ぜひこの研究の知見を役立ててみてください。
参考文献
Older obese individuals have a lower risk of dementia, but there is a big caveat
Older obese individuals have a lower risk of dementia, but there is a big caveat
https://www.psypost.org/older-obese-individuals-have-a-lower-risk-of-dementia-but-there-is-a-big-caveat/
元論文
Association of Body Mass Index in Late Life, and Change from Midlife to Late Life, With Incident Dementia in the ARIC Study Participants
https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000213534
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部