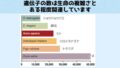久しぶりに散歩したら、去年はススキ野原だった空き地や河川敷が、セイタカアワダチソウばかりになっていた。そんな光景を見かけたことはないでしょうか?
「セイタカアワダチソウ」は、すっかり日本の秋の風景に溶け込んでいますが、もともとは北アメリカ原産の外来種です。
そのため秋の景色を侵食する外来種と嫌う人も多いかもしれませんが、実際はそんなに脅威的な植物でもないようです。
実際、ススキの野原がセイタカアワダチソウに変わったあと、また何年かするとススキの野に戻っているのを見かけたことはないでしょうか?
今回はそんな散歩していてよく見かける、植物たちの不思議な攻防と、意外と知らない植物「セイタカアワダチソウ」について解説します。
目次
- 悪いイメージの多いセイタカアワダチソウ
- なぜススキは戻ってくるのか?
悪いイメージの多いセイタカアワダチソウ
セイタカアワダチソウは明治時代に観賞用や蜜源植物として日本へ持ち込まれたのが始まりで、当初は庭園や養蜂場で栽培されていました。
その後、第二次世界大戦後に急速に野生化し、都市近郊の空き地や河川敷などへ広がりました。特に1940年代後半には、北米からの綿花や軍需物資に混ざって種子が運ばれたことも拡散を助けたといわれています。
実はこのセイタカアワダチソウは根から他の植物の成長を阻害する化学物質を出しており、それによってススキなどの在来種を駆逐して繁殖しています。
セイタカアワダチソウは侵略的外来種に指定されており、背も大きいため威圧感があってあまり良いイメージを持っている人は少ないかもしれません。
ただ、私たちにとってはもはや身近な植物であり、子供の頃から近所の空き地や河川敷で見慣れた親しみ深い植物なのも確かでしょう。
彼らは忌むべき、悪しき植物なのでしょうか? 実のところ、そんな嫌われるほど悪い植物でもないかもしれません。
花粉症の原因という濡れ衣の被害者

セイタカアワダチソウは、見た目がブタクサに似ているために、「すっごい花粉飛ばしそう」というイメージを持つ人が多いようです。
しかし彼らは花粉を飛ばさず、虫を媒介にして受粉を行う虫媒花と呼ばれる種類の植物です。

風に乗せて花粉をばらまくタイプは風媒花と呼びます。そのためセイタカアワダチソウは花粉をばらまいたりはしないのです。
だから花粉症の人たちが、セイタカアワダチソウを見て、あらぬ誤解で敵意を向けないようにしてあげましょう。
敵を化学物質で除外するアレロパシー効果を起こす植物

植物が化学物質を放出し環境に影響を与えることをアレロパシー(Allelopathy:他感作用)と呼びます。
これにはバジルとトマトを一緒に植えるとトマトが甘くなるなどポジティブな効果を指す場合もありますが、逆に他の植物の成長を阻害するネガティブな効果を指す場合もあります。
そしてセイタカアワダチソウは負のアレロパシーを有する植物です。
セイタカアワダチソウは根や枯葉から「cis-DME(シス-デヒドロマトリカリア・エステル)」という物質を放出し、ススキなど在来種の発芽や根の成長を妨げると言われています。
これに加え、その名の通り背の高い植物であり、背の高さで他の植物へ降り注ぐ日光を奪い、勢力を広げているのです。
これが気づけば馴染みの散歩ルートでススキが一掃され、セイタカアワダチソウばかりの景色になっている理由です。
それを聞くと「なんて嫌な植物だ」と思うかもしれません。しかし実のところ、セイタカアワダチソウの繁栄はあまり長く続きません。ススキが消えてセイタカアワダチソウばかりになった、と思っていた人は、何年か後にセイタカアワダチソウが消えて、またススキが復活しているのを目にした覚えがあると思います。
この変化に気づいている人は、「なんでだろう?」と疑問に思ったかもしれません。こうした景色の変化はなぜ起きるのでしょうか?
なぜススキは戻ってくるのか?
セイタカアワダチソウに取って代わられた後、その土地に数年後、再びススキが勢力を取り戻していることがあります。
これは偶然ではありません。ではどのような理由でこの循環が起きるのでしょうか?
まず、セイタカアワダチソウが密集しすぎると、根のまわりの酸素や栄養が不足していきます。また密集して繁殖したことで、枯れた茎や葉が厚く積もって地表を覆うため、これも新しい種子が根付いて発芽することを妨げます。
さらにセイタカアワダチソウは自分で出した化学物質が土壌にたまることで、自分たちの発芽すら妨げてしまう「自家中毒」状態に陥ると言われています。
そのためセイタカアワダチソウは、一度は繁栄するもののその状態は長続きせず、繁殖が難しい状態に陥ってしまうのです。
その隙を狙うのがススキです。
ススキは地下茎を広く張り巡らせ、地上部が一時的に負けても地面の下で根がじっと生き延びる粘り強い植物です。枯れ葉や茎の層が地面を覆ってもススキはその影響を受けません。そのためセイタカアワダチソウが衰えると、ススキの地下茎が再び芽を出し、空いた空間を埋めていきます。
こうして、数年のうちに再びススキの野原が戻るのです。

共存する自然のバランス
しかしススキが巻き返してしばらくすると、またセイタカアワダチソウの種子が風に乗ってやってきて発芽し、ススキと勢力を入れ替えながら共存が続きます。
このように、セイタカアワダチソウが光と化学物質でススキを圧倒しても、その後密集しすぎる繁殖力と自分の毒で勢いを失い、ススキが再び巻き返す――彼らは、そんなせめぎ合いを秋ごとに繰り返しているのです。
このためセイタカアワダチソウは爆発的な繁殖力で、在来種を脅かす危険な存在のようにも感じますが、長い期間観察していると、そうでもなかったりします。
もし散歩中に彼らを眺めることがあったら、今回の話を思い出して植物の勢力図がどのように変化していくか、観察してみると面白いかもしれません。
またセイタカアワダチソウが日本に入ってきたのは明治の頃で、ミツバチなどの虫たちにとってはもはや貴重な蜜源にもなっています。
見慣れたススキの景色が彼らに取って代われたら確かにショックですが、そんなに嫌わないであげてもいいかもしれません。
花粉症の原因じゃないかと疑いの目を向けられたり、侵略的外来種と言われつつ最終的にはススキに巻き返されてしまう、そんなセイタカアワダチソウを見かけたら温かい目で見守ってあげましょう。
※なおここに記したセイタカアワダチソウの化学作用や繁殖メカニズムについては、実験室では確認されていますが、自然環境の観察では土壌や天候など多くの要因が絡み合って確認が難しく、完全には解き明かされていません。
参考文献
セイタカアワダチソウ、もっと身近に・・・(額田医学生物学研究所)
https://nukada.jimdo.com/%E8%96%AC%E8%8D%89%E5%9C%92/%E8%96%AC%E8%8D%89%E5%9C%92%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%80%E3%83%81%E3%82%BD%E3%82%A6/
元論文
Mowing inhibits the invasion of the alien species Solidago altissima and is an effective management strategy
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1410532/v1
セイタカアワダチソウのcis-dehydromatricaria ester含有量および放出量(PDF)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/weed1962/41/4/41_4_359/_pdf
ライター
海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。
編集者
ナゾロジー 編集部