カナダのコンコルディア大学(Concordia University)で行われた研究によって、「人間の睡眠は5つのタイプに分かれる可能性」が明らかになりました。
研究チームは、米国の若年成人770人の脳と睡眠習慣を同時に分析し、眠り方の違いが健康状態や思考力、さらには脳内ネットワークの“配線”の違いとして現れることを突き止めました。
「眠り方のクセ」は心や体だけでなく、脳そのものに刻まれているかもしれないというのです。
これまで「8時間寝れば十分」と言われてきた常識は、どうやら一人ひとりに当てはまるわけではないようです。
では、あなたの睡眠タイプはどんな“脳の眠り方”をしているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月7日に『PLOS Biology』にて発表されました。
目次
- 「よく寝てもダメ」な理由は脳のクセにあった
- あなたの睡眠はどのタイプ? 脳に刻まれた眠り方のクセ
- あなた専用の睡眠アドバイスが必要な理由
「よく寝てもダメ」な理由は脳のクセにあった

「8時間寝れば万事OK」って、本当でしょうか?
世の中には、「ちゃんと8時間寝ないと身体に良くない」とか、「睡眠時間は7~8時間が理想だ」といった、いわゆる睡眠の「常識」があふれています。
もちろん、寝不足が良くないことくらいは誰でも経験で知っているでしょう。
実際、睡眠時間が短い日には「ああ、眠い…」とついぼやきがちです。
ところが、よく見てみると私たちの周りには、短い睡眠時間でもケロッとして元気な人もいます。
かと思えば、しっかりと長時間寝ているはずなのに「ぜんぜん疲れが取れない」と訴える人もいます。
ここでふと疑問に感じませんか?
「眠りって、時間だけで決まるほど単純なものじゃないのかも…?」と。
睡眠というのは予想以上に複雑なものです。
睡眠の専門家によれば、眠りには「長さ(量)」だけではなく、「質」や「深さ」、さらには「毎日の規則性」や「どの時間帯に寝ているのか」など、多くの側面があります。
これを料理に例えるなら、ただ「適量食べれば健康になる」というほど単純ではないように、「睡眠もただ推奨時間だけ寝れば良いというわけではない」のです。
つまり、「睡眠時間」と「睡眠の質や満足感」というのは必ずしもイコール(比例関係)ではないわkです。
ところが、これまでの睡眠研究は少し事情が違いました。
多くの研究では「睡眠時間と健康の関係」や「睡眠の質と心の状態の関係」といったように、特定の1つの要素に絞って、その影響を調べるという方法が主流でした。
もちろん、こうした単発的な研究でも貴重な成果が得られています。
例えば、「睡眠不足になると集中力や記憶力が低下する」とか、「睡眠の質が悪いとメンタルが不調になる可能性がある」などです。
ただ、このような研究だけを積み重ねても、睡眠という現象の「全体像」をうまく捉えることは難しいのです。
というのも、睡眠というのは本質的にさまざまな要素が絡み合って起きる「複雑な現象」だからです。
複数の要素が複雑に絡んでいるときに、要素を1つずつバラバラに調べても、本当に起きていることを理解するのは難しくなります。
これはちょうど、「料理を味わう時に、食材を別々に食べるだけではその料理の全体的な美味しさは伝わりにくい」のと同じです。
そこで今回の研究チームは発想を変えました。
彼らは睡眠に関わるさまざまな要因を、バラバラにではなく「一度にまとめて」分析する方法を使って、「人の眠り方の違い」を分かりやすく見える化しようとしたのです。
では、このように複数の要素を同時に見ることで、一体どんなことが明らかになったのでしょうか?
人間の睡眠が本当に5つものタイプに分かれるとしたら、その「眠りの個性」の正体とは一体どんなものなのでしょうか?
あなたの睡眠はどのタイプ? 脳に刻まれた眠り方のクセ

この研究チームは、若者の脳と睡眠を大規模に調べた研究プロジェクト『ヒトコネクトーム計画(HCP)』のデータを利用しています。
HCPというのは簡単に言えば、「人間の脳のしくみ」を詳しく調べるための大掛かりなプロジェクトです。
この計画では、睡眠障害を抱えていない、健康な若い成人770人に、睡眠習慣を細かく質問したアンケートを実施しました。
具体的には、「寝付きの良さ」や「睡眠時間」、「夜中に目が覚める回数」など、さまざまな睡眠に関する情報を聞き取りました。
また、この770人は、睡眠以外にも認知テスト(集中力や記憶力を測るテスト)や心理状態をチェックするアンケート、さらには生活習慣についても詳しく質問されています。
こうして睡眠のことだけでなく、心や体、頭の働き方、日々の生活スタイルまで、幅広い情報が集まったわけです。
さらに面白いのは、このうち多くの参加者(解析対象は723名)については、fMRI(機能的MRI:脳の活動を映像化する方法)という最新の技術を使って、脳の活動状態まで詳しく記録した点です。
MRIというと「病院で脳や体の写真を撮る装置」と思う人もいるかもしれませんが、fMRIでは脳が働いている時の活動をリアルタイムで見ることができます。
まさに脳の動きを撮影する「脳の動画撮影」みたいな技術なんです。
さて、研究チームは、こうして集めた膨大なデータをどう扱ったかというと、ちょっと特別な方法で解析をしました。
通常の研究では、一つの要素を取り上げてそれが睡眠にどんな影響を与えるかを調べますが、今回の研究ではあえて逆をやっています。
つまり、「睡眠についての情報」と「心身の健康状態・認知能力・生活習慣など」のデータを全部ひっくるめて同時に分析し、「睡眠のパターン(タイプ)」を見つけようと試みたわけです。
その結果、たとえ睡眠に問題がない人々であっても、その睡眠は大きく5つのタイプに分けられる可能性があることが分かりました。
1つ目のタイプは、典型的な「睡眠が不調なタイプ」です。
このタイプは眠りへの満足感が低く、寝付くまでに時間がかかり、夜中に何度も目が覚めるといった、いわゆる不眠症に近い症状が出ていました。
予想通り、このタイプの人はストレスや不安感、気分の落ち込みなど、心理的にも問題を抱えている傾向が強かったのです。
脳深部の領域(サブコルチカル領域)と、 体を動かしたり感覚を処理する部分(体性感覚運動ネットワーク)、そして外の世界に注意を向けるネットワーク(背側注意ネットワーク)との間で“つながり”が強くなる傾向が示されています。
一方で、自己を振り返る・思考を内側に向けるネットワーク(TPN=テンポロパリエタルネットワークなど)とはつながりが弱くなる傾向も見られました。
2つ目のタイプは、「睡眠レジリエンス(回復力)」タイプと名付けられました。
このタイプの人は、実は心理的にはかなりストレスを感じたり、注意力の低下などメンタル面で問題を抱えているのですが、なぜか睡眠だけは良好な状態を保っているという面白い特徴があります。
簡単に言えば、「心がしんどくても睡眠は意外と平気」という眠りの強さを持ったグループです。
睡眠不良タイプ(LC1)ではメンタル不調が睡眠にも悪影響を及ぼしていましたが、このレジリエンスタイプ(LC2)では睡眠がある程度守られていることが明らかになったのです。
まさに「睡眠の体質」の違いともいえるでしょう。
ただ脳には明白な変化がみられ、外に注意を向けるネットワーク(背側注意ネットワーク)と、思考や行動をコントロールするネットワーク(制御ネットワーク=認知制御系)との結びつきが強まる傾向がありました。
その一方で、背側注意ネットワークと自己思考系・感情系ネットワーク(TPN、辺縁系など)とのつながりは弱くなる傾向がありました。
残りの3つのタイプは、さらに個別的な特徴を示していました。
まず3つ目は「睡眠薬を常用するタイプ」です。
このタイプの人は眠れないことが多いために睡眠薬をよく使用しています。
意外なことに、このグループでは日中の眠気や注意力の低下はあまり見られず、記憶テストや感情を読み取るテストでの成績が少し低めでした。
さらに対人関係への満足度が比較的高いという、不思議な特徴を示していました。
これらの人々の脳では見た情報を処理するネットワーク(視覚ネットワーク)**や、自分の考え・記憶・内的活動を司るネットワーク(デフォルトモードネットワーク)内では、部位どうしの“つながり”が強くなる方向の変化が観察されました。
また、他のネットワークとの混ざり合いが少なくなりやすい(分離傾向)、つまり外部とのつながりが相対的に弱まる特徴も示されました。
4つ目は「短時間睡眠タイプ」で、毎晩6〜7時間未満しか眠らない人たちです。
睡眠時間が短い影響が明確に出ており、認知力テストの正答率が低く、回答にかかる反応時間も長めでした。
また、攻撃的な傾向があり、協調性も低いという性格的な特徴もありました。
このタイプの場合は複数のネットワークが、“つながりが強くなる部分”も“弱くなる部分”も混在するような変化を示しており、あちこちで再編成が起きている様子がみられました。
特に体性感覚運動ネットワーク(体を動かしたり感じたりする部分)では、“内部と外部とのバランス”が変動しており、ネットワークの統合と分離(複数の部位がまとまるか、逆に独立性を保つか)が変動している傾向がありました。
これは睡眠不足の影響を反映している可能性があります。
最後の5つ目のタイプは、「睡眠が分断されるタイプ」です。
睡眠が何度も中断されることが特徴で、夜中に目が覚めたり、トイレに立つ回数が多い人、いびきや呼吸の乱れで目覚めやすい人が含まれます。
認知テストでもあまり良い結果が出ておらず、不安感や思考の混乱、さらにはアルコールやタバコの摂取量が多いなど、さまざまな問題を同時に抱えやすいことが分かっています。
このタイプの脳は体性感覚運動ネットワーク、背側注意ネットワーク、腹側注意ネットワークなど、それぞれのネットワーク内部での結びつき(内部結合)が弱まる傾向がありました。
研究者は、これらの脳のネットワークの違いが「睡眠の問題に対する脆弱性や耐性」を示している可能性があると考えています。
言い換えるなら、「同じようなストレスを抱えていても、眠れなくなる人と平気な人の違い」は、脳のつながり方に秘密があるのかもしれない、ということです。
今回の研究で見えてきた5種類の分類は一見すると睡眠障害の分類のように見えますが、参加者は全て健康であることが重要なポイントです。
つまり健康な人であっても、1人1人が睡眠の位置に座標を持っており、この5分類のいずれかの傾向に寄るということを意味します。
あなた専用の睡眠アドバイスが必要な理由
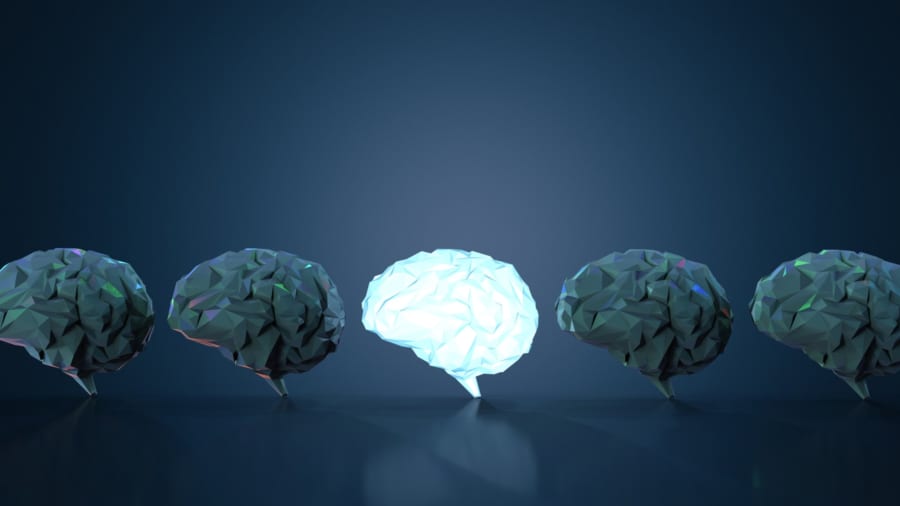
今回の研究は、睡眠をただ「良い」「悪い」で単純に二分する考え方を見直す、大きなきっかけになりました。
睡眠というと、私たちはつい「睡眠時間さえ確保できれば健康に良い」「眠りが悪ければ健康に悪影響がある」と考えがちです。
ですが、この研究は、「睡眠は単純な『時間の長さ』では測れない、多様な特徴を持っている」ことを改めて気付かせてくれたのです。
実際、今回の研究では700人以上もの若者を対象に、非常に多くのデータを同時に分析して、人間の睡眠が5つのタイプに分かれる可能性を示しました。
研究チームによると、「睡眠は単なる時間の問題だけでなく、さまざまな要素が絡み合って成り立っていることが分かりました。私たちは5つの『睡眠プロファイル』を特定しましたが、それぞれのタイプが、心や体の健康、日常生活、認知機能などと独自の結びつきを持っていることが確認されました」と述べています。
さらに、脳の活動を調べるMRIという装置でそれらの睡眠タイプを比較したところ、タイプごとに脳のネットワークにも特徴的な違いが見つかりました。
つまり、「睡眠タイプの違いは、心や身体だけでなく、脳の働き方にも関係している可能性があります」というわけです。
これは、睡眠というテーマにおいて、非常に興味深い視点の変化をもたらします。
睡眠の専門家たちがよく指摘するように、睡眠に関する指導や治療というのは、これまでどうしても一律になりがちでした。
例えば「夜11時までには寝ましょう」「毎日8時間寝ましょう」といった画一的なアドバイスが主流だったわけです。
ところが、この研究が示したように、私たちの睡眠が実際には5つものタイプに分かれるとしたら、同じアドバイスが全員に効くとは限りません。
あるタイプには効果があっても、別のタイプにはむしろ逆効果になる可能性だってあります。
研究者たちは、「睡眠のタイプごとに、より個人に合った指導や改善の方法を探ることが今後の課題です」としています。
例えば、睡眠の質が悪い人には睡眠環境を整えたり、心理的なケアを取り入れるなどの工夫を。
逆にメンタルの問題があっても睡眠が守られているレジリエンスタイプには、別のアプローチを考える必要があるかもしれません。
言ってみれば、「自分専用の睡眠改善法を見つけられるようになる可能性がある」というわけです。
とはいえ、この研究にも注意すべき限界や課題はあります。
まず、この研究はあくまで観察研究というタイプの研究です。
つまり、「睡眠が悪くなると健康やメンタルが悪化する」などという直接的な原因と結果の関係(因果関係)を証明することまではできていません。
こうした限界があるとしても、今回の研究は大きな意義を持つ発見です。
研究チームは今回の研究で使用したデータや解析コードをすべて公開しており、他の科学者たちが追試験を簡単にできるよう環境を整えています。
これによって、世界中の研究者が新たな視点で睡眠を再検討し、さらに理解を深められるようになるでしょう。
元論文
Identification of five sleep-biopsychosocial profiles with specific neural signatures linking sleep variability with health, cognition, and lifestyle factors
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003399
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


