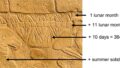人生のピークと言われると何歳くらいを思い浮かべるでしょうか?
仕事でも生活でも、「考える速さ」や「新しい問題への反応の良さ」など脳処理の速さや、肉体的な健康さが最も高くなるのは18〜25歳ごろとされています。
そのため、多くの人が「人生のピークは20代」と思い込んでいます。
しかし、日々の判断力や対人関係、経験に裏打ちされた知恵まで含めて考えると、話は少し違ってくるかもしれません。
オーストラリアの西オーストラリア大学(University of Western Australia)の心理学者ジル・ギニャック(Gilles E. Gignac)氏と、ポーランドのワルシャワ大学(University of Warsaw)のマルチン・ザジェンコフスキ(Marcin Zajenkowski)氏による新たな研究は、既存の人間のピークに関する認識は間違っている可能性を指摘しています。
彼らによると、推論力や記憶力など脳の処理速度だけでなく、語彙や知識、性格特性、感情の扱い方、道徳的推論などを幅広く調べた結果、人間が総合的に最もうまく機能するのは若年期ではなく、55〜60歳前後の可能性があるという。
この研究の詳細は、2025年9月付けで科学雑誌『Intelligence』に掲載されています。
目次
- 人間の総合的なピークはどこにあるのか?
- 重要なのは“瞬発力”より“調和”、ピークは55〜60歳
人間の総合的なピークはどこにあるのか?
人間の多くの能力は20代でピークを迎え、以降は衰えていく一方であると言われます。
肉体的にも20代を終えると急激な衰えを感じる人は多く、発想やひらめき、記憶力といった脳機能の面でも若い人には叶わないと感じている人は多いでしょう。
実際多くの研究が脳処理の能力は20代がピークであることを報告しています。
こうした知見が、「若さこそが能力のピーク」というイメージを支えてきました。
しかし、人間の能力は単純な瞬発力だけでは測れません。
知能においては語彙や知識、経験を通じて培われる判断力など、時間をかけて伸びていく力もあります。
こうした違いを比較して、心理学では新しい状況で柔軟に考える力を「流動性知能(fluid intelligence)」、学習や経験によって“固まっていく知恵”を「結晶性知能(crystallized intelligence)」と呼んでいます。
そして、結晶性知能については年齢とともに上昇し、60代でも高水準を維持することが多いと報告されているのです。
また、収入や職位、リーダーシップの発揮など社会的な成功は50〜55歳にピークを迎えるという報告もあります。
それにもかかわらず、人間の能力や人生の充実のピークがどこにあるかという議論において、「心や思考の成熟」はこれまでの知能研究では十分に扱われてきませんでした。
そこで今回の研究者は、「人が最もうまく機能する年齢」を総合的に見直すことを目指して調査を行うことにしました。
研究では、速さを測る知能検査に加えて、誠実性や情緒安定性などの性格特性、感情を理解し調整する力(感情知能)、お金に関する知恵(金融リテラシー)、道徳的推論、そして「一度費やしたからやめられない」といったサンクコストの罠への抵抗力まで、16種類の心理的要素を評価対象としました。
それぞれのデータを共通の「Tスコア」(平均50、標準偏差10)に統一し、年齢ごとの変化をなめらかに描くために「LOESS回帰」という統計手法を使用しました。
さらに、社会的な重要性に応じて重みを与え、「CPFI(Cognitive–Personality Functioning Index:認知・人格機能指数)」という総合スコアを作成しました。
このCPFIには2つのモデルが用意され、1つは知能と性格特性を中心にした「従来型モデル」、もう1つは感情知能や金融知識なども含めた今回の研究が目指す総合力を示す「包括型モデル」です。
こうして研究者たちは、単なる脳の処理速度にとどまらず、人格特性や感情の扱い方、判断力なども含めて総合的な能力が人生でもっとも上手く機能している時期を特定したのです。
重要なのは“瞬発力”より“調和”、ピークは55〜60歳
研究の結果、「従来型モデル」と「包括型モデル」ではピークの年齢がまったく異なることがわかりました。
従来型モデルは、主に流動性知能(新しい問題を素早く解く力)を重視しており、20代前半で総合スコアが最も高くなっていました。このモデルでは、若い世代ほど脳の処理速度や柔軟な思考力が高く、年齢とともにその能力が徐々に低下していく傾向を示していました。
一方、感情知能(自分や他者の感情を理解し調整する力)、金融リテラシー、道徳的判断力といった“経験によって育つ力”も含めた包括型モデルでは、55〜60歳で明確なピークを示しました。このモデルの曲線は、若年期から中年期にかけて上昇し続け、60歳前後で最も高くなったのです。
つまり、脳の処理能力は加齢で低下するものの、それは単純に人間の能力の衰えを意味するわけではなく、複数の能力が最もバランスよく調和するのは年齢を重ねた後だということを示しています。
この結果は実社会の状況ともよく合っています。
収入や職位のピークは50〜55歳にあり、多くの国の首相や大統領が就任する年齢も50代後半から60代前半に集中しています。
つまり、人が「最も複雑な判断を下せる時期」は、社会の実情にも反映されているのです。
さらに詳しく見ると、語彙や知識を基盤とする結晶性知能は年齢とともに上昇を続け、60代でも高水準を保っていました。
金融リテラシーも60代後半まで向上しており、経験が知恵へと変わっていく様子を示しています。
また、誠実性や情緒安定性は中年で高まり、対人関係の安定に寄与していました。
感情知能や道徳的推論、そしてサンクコストの罠(投資額に応じて誤りだと感じても途中でやめられなくなる現象)への抵抗力も、年齢とともに強くなっていました。
一方、流動性知能(新しい問題への対応力)や認知的柔軟性、認知的共感(共感の敏感さ)、新しい知識を求める意欲(認知欲求〔Need for Cognition〕)は加齢で低下していましたが、それらは他の能力によって補われ、全体としての機能はむしろ上昇していました。
研究者のギニャック氏は一般向け解説の中で、「55〜60歳の強みは、複雑な課題を冷静に処理し、異なる立場の人々をまとめる力にある」と述べ、雇用における年齢バイアスの見直しを呼びかけています。
感情の制御、倫理的な判断、社会的知識といった“経験で伸びる力”も向上する、現実の暮らしにおいて、より落ち着いた判断・人間関係の安定・自分らしい価値判断がしやすくなることを意味します。
社会的な立場も安定している60歳前後は、幸福感や人生の充実感が最も実感されやすい時期なのかもしれません。
若さこそが人生の充足に重要で、歳を取るとあらゆる能力が低下して満足感も下がると認識する人は多いですが、実際の人生の安定したピークはかなり人生の後半に訪れるようです。
参考文献
Worried about turning 60? Science says that’s when many of us actually peak
https://theconversation.com/worried-about-turning-60-science-says-thats-when-many-of-us-actually-peak-267215
元論文
Humans peak in midlife: A combined cognitive and personality trait perspective
https://doi.org/10.1016/j.intell.2025.101961
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部