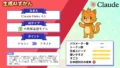アメリカのウィリアム・アンド・メアリー大学(W&M)に所属するヴァージニア海洋科学研究所(VIMS)で行われた研究によって、外洋の夜の海で幼い魚たちが、イソギンチャクの幼生を“刺すお守り”のように持ち歩いている驚きの行動が正式に観察記録として報告されました。
研究チームは、フロリダ沖やタヒチ沖での夜間潜水によって撮影された写真を分析し、カワハギやアジなど4つの魚のグループが、刺す能力を持つイソギンチャクの幼生を防御に利用している可能性を発見しました。
まるで自分の体を守るために“毒針付きの盾”を持ち歩くかのようなこの行動は、魚とイソギンチャクの共生関係がサンゴ礁だけでなく、広大な外洋でも成立しうる可能性があることを示唆しています。
この発見により、映画『ニモ』で描かれるイソギンチャクと魚の共生が実はもっと多様で、サンゴ礁だけでなく広大な外洋でも起こりうる可能性が示唆されました。
しかしなぜこのような愉快な姿は今まであまり知られていなかったのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年9月5日に『Journal of Fish Biology』にて発表されました。
目次
- 小さな魚が見つけた意外な守護者
- 小さな魚が持ち歩く「刺すパートナー」
- まとめ:幼魚とイソギンチャクの新たな関係—これは「相利共生」なのか?
小さな魚が見つけた意外な守護者

魚が自分で「お守り」を持ち歩くなんて、なかなか想像できない光景です。
しかし、広く深い海の中で小さな魚の赤ちゃんたちが生き残ろうと必死になった結果、この驚きの作戦が生まれたのかもしれません。
私たちがよく知る魚とイソギンチャクの関係といえば、カクレクマノミをすぐ思い浮かべますよね。
映画『ファインディング・ニモ』の主人公「ニモ」でおなじみの、あのオレンジ色の小さな魚です。
カクレクマノミはサンゴ礁の海で暮らしていて、刺す能力をもったイソギンチャクの中に隠れることで敵から身を守っています。
毒針を持ったイソギンチャクを「家」として利用することで、安全な場所を確保しているんですね。
しかし、これはあくまでサンゴ礁や岩場の話です。
サンゴ礁は生き物たちが暮らすための隠れ場所が豊富ですが、外洋と呼ばれる広大で深い海の表面近くには、そんな都合のいい「家」になる場所はありません。
外洋は基本的に開けていて、隠れ場所がほとんどない世界です。
そんな外洋の厳しい環境で、幼い魚たちはどうやって身を守るのでしょうか?
実はこれまでにも、幼魚たちがクラゲなどの漂っている生き物に隠れて敵から逃れていることが報告されてきました。
少なくとも21科の幼魚が、クラゲやそれに似た漂う生き物を「動く隠れ家」として使うことが知られています。
ところが、この幼魚とクラゲの関係は、片利共生(かたりきょうせい)という一方的な関係だと考えられてきました。
片利共生とは、片方だけが利益を得て、もう片方には特にメリットもデメリットもない関係のことです。
幼魚はクラゲに隠れることで敵から身を守れるので得をしますが、クラゲ側は特に幼魚から得るものはありません。
むしろ、幼魚がクラゲをかじって食べてしまうことすらあるのですから、クラゲにとっては「食べ放題にされて迷惑だ」と感じる場合もありそうです。
さて、ここまでの話は、幼魚がクラゲなどの生き物に「隠れている」というだけでしたが、幼魚がイソギンチャクの幼生を自ら「持ち歩く」ことはないのでしょうか?
実は近年、この驚きの関係の手がかりを与えてくれたのが「ブラックウォーターダイビング」という新しい調査方法です。
ブラックウォーターダイビングとは、真っ暗な夜の外洋に潜って、ライトを当てながら小さな生き物を撮影する潜水方法です。
夜になると、多くのプランクトンや魚の幼生が暗い海の浅いところまで浮かび上がってくるため、夜の海はまるで「真っ暗な動物園」のような世界になっています。
こうした小さな生き物たちは昼間は見つけることが非常に難しいため、ブラックウォーターダイビングで初めて観察されるケースが増えているのです。
この方法で撮影された写真を研究者たちがじっくり分析したところ、外洋の幼魚がイソギンチャクの幼生を口にくわえたり、体のそばに置いたりして一緒に漂っている奇妙な様子が写っていたのです。
これを見た研究チームは「これは新しい関係なのではないか?」と考え、正式にこの関係を記録して報告することを目指しました。
まずは、実際にそうした関係が外洋で観察されたことをきちんと報告することが大切です。
さらに、幼魚とイソギンチャクがお互いに利益を得ている「相利共生(そうりきょうせい)」という関係になっている可能性を、ひとつの仮説として提案することが目的でした。
では、本当に幼魚はイソギンチャクを利用して敵から身を守れるのでしょうか?
そして、もしそうなら、イソギンチャク側にも何らかのメリットがあるのでしょうか?
これらの興味深い謎を明らかにするために、研究チームは外洋の不思議な世界にカメラのレンズを向けたのです。
小さな魚が持ち歩く「刺すパートナー」

研究チームがまず行ったのは、2018年から2023年までの5年間、フロリダ沖(アメリカ)やタヒチ沖(仏領ポリネシア)で撮影された膨大な夜間潜水の写真を丁寧に分析することでした。
さて、問題の写真には、体長わずか数ミリから数センチという、とても小さな魚たちがたくさん写っていました。小指の爪より小さいような幼魚たちです。
彼らが何の種類の魚なのかを特定するためには、ヒレの形や棘の数、体の模様といった細かな特徴を手がかりにします。ちょうど人間の指紋で個人を見分けるように、小さな魚たちにもちゃんと識別できる目印があるのですね。
そんな風に写真をよく調べてみた結果、4つの異なる「科」(魚の種類を大きく分けるグループ)の幼魚が、漂うイソギンチャクの幼生とセットになっていることが分かりました。
それが、アジ科・マナガツオ科・アリオマ科・カワハギ科の幼魚たちでした。
しかも、それぞれの幼魚がイソギンチャクを利用する方法もさまざまでした。
カワハギの幼魚は、小さなスナギンチャク科(パリトア属)の幼生を口にくわえて運び、自分の身を守るように泳ぎ回っていました。
また、アリオマ科の幼魚はチューブイソギンチャク(細長い筒状のイソギンチャク)の幼生に寄り添いながら、まるでボディガードに護衛されるようにしていました。
さらに興味深かったのは、マナガツオ科(Brama)の幼魚のケースです。
彼らもイソギンチャクの幼生を口にくわえていましたが、中には腹ビレ(お腹の部分にある小さなヒレ)で幼生を抱えるようにして「乗り物」のように使っている魚もいました。
まさに「動く武器庫」のような使い方をしていたわけです。
最も印象的な行動を見せたのが、カワハギの仲間です。
この幼魚はイソギンチャクを口にくわえたまま活発に泳ぎ回り、研究者が観察のために近づいた際にも防御のような姿勢を取る様子が見られました。
そして、しばらくして幼魚がイソギンチャクを放して泳ぎ去ったあとも、そのイソギンチャクには傷がありませんでした。
まるで幼魚が力加減を心得ているかのようですね。
また、アジ科の幼魚(Caranx cf. latus)も興味深い行動を見せました。
ダイバーが近づくと、自分とダイバーの間にチューブイソギンチャクの幼生がくるように素早く位置取りを変え、生きた盾のように使っているように見えました。
ここで疑問がわきます。
「そんな小さなイソギンチャクが盾になるほど強力なのか?」と。
実は、イソギンチャクの幼生も小さいながら「刺胞(しほう)」という小さな毒針を持っていることがあります。
もちろん、この毒は大型の捕食者を倒せるほど強烈ではありませんが、魚の赤ちゃんを食べようとする相手に対して「これを食べると痛い目に遭うぞ」と思わせるには十分な刺激になるかもしれません。
例えば、辛すぎるトウガラシを一度かじってしまったら、次からはもう食べようとは思いませんよね。
幼魚にとっては、このイソギンチャクがまさに「小さな電気クラゲ」のような存在として役立っていると考えられます。
まとめ:幼魚とイソギンチャクの新たな関係—これは「相利共生」なのか?
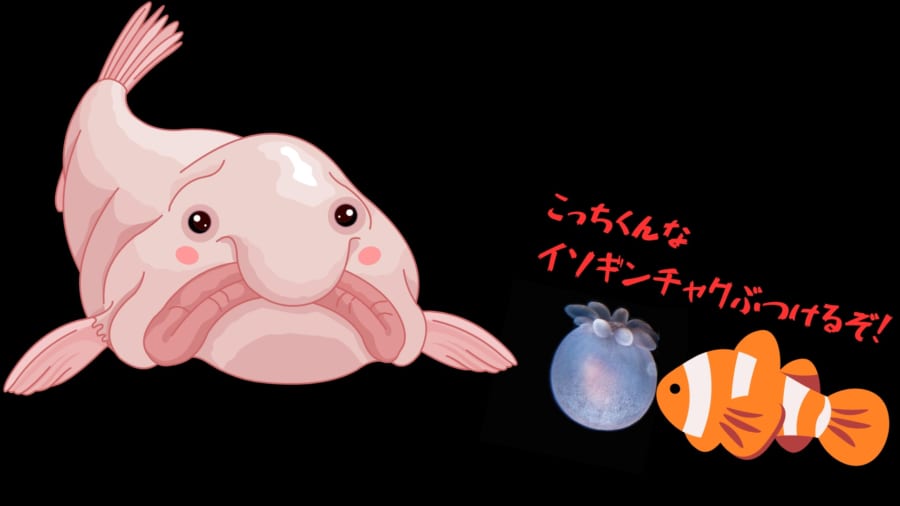
今回の研究を通して、小さな魚たちが外洋という過酷な環境の中で、生き延びるための意外な戦略を持っていることが示されました。
それはまるで、自分で武器を選び、装備するような、巧みでユニークな行動でした。
実は今まで、イソギンチャクと魚の関係はサンゴ礁などの限られた場所でのものだと考えられてきました。
しかし、今回の発見によって、広い外洋という「隠れ場所がほとんどない世界」でも同じような戦略が観察によって示されたのです。
幼魚たちは「刺す能力」を持った小さなイソギンチャクを自ら持ち歩くことで、自分自身を敵から守る方法を見つけ出していました。
それは言ってみれば「小さな魚が毒針つきの護衛を連れて歩く」ようなものですね。
今回の発見は単なる珍しい行動の目撃報告にとどまりません。
生き物たちが自分の身を守るためにいかに創造的な戦略を進化させるか、その一端を私たちに教えてくれる貴重な例なのです。
これまで、幼魚たちが身を守る方法としてよく知られていたのは、クラゲなど漂う生き物に単純に隠れるというものでした。
しかしこの研究では、幼魚たちが積極的に生き物を選び、それを利用しているように見えるという点で、従来の知見とは明らかに違っています。
この違いはとても重要で、これまでの受動的な防御方法に対して、能動的に見える防御方法という新しい可能性を提起しているのです。
また、研究チームはさらに面白い仮説も提示しています。
それは、この関係が単に魚だけが得をする「片利共生(かたりきょうせい)」ではなく、両方にメリットがある「相利共生(そうりきょうせい)」かもしれないということです。
もし幼魚がイソギンチャクの幼生を連れて泳ぎ回ることで、幼生の方も新たな場所にたどり着きやすくなればどうでしょうか。
普段は自分ではほとんど動けないイソギンチャクの幼生にとって、魚の移動に便乗するのは「新しい場所を見つけるチャンス」を得たようなものかもしれません。
これはあくまで仮説ですが、とても興味深い提案で、さらなる研究によって詳しく検証される価値があります。
もちろん、今回の研究にはいくつかの限界もあります。
たとえば、観察された例の数はまだ少なく、この現象が一般的なものなのか、偶然の産物なのか、はっきりとは言えません。
また、幼魚がどれくらいの時間イソギンチャクを持ち歩くのか、本当に捕食者からの防御に役立つのかといった具体的なデータは、まだ十分ではありません。
ここで提示された相利共生という仮説を実証するには、さらなる詳しい観察や実験が必要なのです。
しかし、だからといって今回の発見が重要でないわけではありません。
これまで見えていなかった外洋の「知られざる生態系」の一部を写真で捉えたこと自体、極めて貴重な成果です。
こうした写真記録は、研究者や科学者だけでなく、一般の人々やダイバー、水族館や教育現場にも新しい視点を与えるでしょう。
特にダイビングを趣味とする人にとっては、自分が潜っている海が実は未知の生物同士の不思議な関係であふれていると知ることは、大きな喜びと驚きをもたらすに違いありません。
また、この研究の背後にある「ブラックウォーターダイビング」という新しい観察手法の重要性も見逃せません。
従来の標本採集や調査手法では決して見ることのできなかった生物の生きた姿や行動を、鮮明な写真で記録することができました。
こうした新しい技術が、今後さらに海の生き物に関する発見を加速させていくことが期待されますね。
参考文献
Blackwater photos suggest new symbiosis between fish and anemones
https://www.eurekalert.org/news-releases/1101041
元論文
Associations between fishes (Actinopterygii: Teleostei) and anthozoans (Anthozoa: Hexacorallia) in epipelagic waters based on in situ records
https://doi.org/10.1111/jfb.70214
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部