イギリスのMRC分子生物学研究所(MRC-LMB)で行われた研究によって、大腸菌に対して実に10万箇所以上のDNAを書き換えるという前例のない大規模な再設計を実施し、アミノ酸を指定する指定札(コドン)を64種類から57種類に大幅に減らすことに成功しました。
これは言語でたとえれば、あらゆる単語の意味を統一する大規模なシンプル化と言えます。
理論上、このように人工的に設計された遺伝暗号をもつ細菌は、ウイルスが増殖のために必要とする遺伝暗号をあらかじめ取り除いているため、ウイルスに感染されにくい細菌として産業や医学への応用が期待されています。
このような遺伝暗号の大胆な書き換えは、節約されたコドン部分に自然界には存在しないアミノ酸を組み込んだ新しいタンパク質や医薬品の生産、さらには環境中でも安全に働くことのできる人工生物の実現へ向けた重要な第一歩となる可能性を秘めています。
果たして、この遺伝暗号の書き換えが、生命のあり方や私たちの暮らしにどのような変化をもたらすのでしょうか?
研究内容の詳細は7月31日に『Science』にて発表されました。
目次
- 『なぜ生命の暗号はムダだらけ?――遺伝コード削減の狙いとは
- 10万か所以上の修正で遺伝暗号の根本を削った
- 【まとめ】人工的に設計された生命「Syn57」は世界をどう変えるか?
『なぜ生命の暗号はムダだらけ?――遺伝コード削減の狙いとは

私たちの身体をつくるための情報は、すべてDNAという物質に書き込まれています。
このDNAは、「A」「T」「G」「C」という4種類の化学文字(塩基)の並びでできています。
この化学文字を3つずつ組み合わせたものが「コドン」と呼ばれる遺伝情報の単語で、それぞれのコドンがどのアミノ酸を使うかを指定しています。
こうして指定されたアミノ酸が、数珠つなぎになってタンパク質が作られます。
言ってみれば、DNAはタンパク質という生命活動の主役を作るための設計図のようなものです。
しかし、このDNAの設計図にはちょっと不思議な特徴があります。
それは、20種類のアミノ酸しか使っていないのに、なぜかアミノ酸を指定するコドン(指定札)は64通りも用意されていることです。
アミノ酸は20種類だけなのに、コドンは64通りもあるということは、当然、余分なコドンが生まれます。
(※理論上は20種類のアミノ酸に対してそれぞれ1つのコドンが対応する20通りに加えて、開始と終わりを示すコドンをプラスして22通りまで圧縮できると考えられています。)
実際、ほとんどのアミノ酸は1つだけのコドンではなく、複数のコドンを持っています。
例えば「セリン」というアミノ酸は、なんと6通りのコドンで表現できます。
これは同じ意味を持つ言葉がたくさんあるのと似ています。
挨拶をするときに「おはよう、こんにちは、こんばんわ」や「やあ」「おはよう」「どうも」など、いろんな表現があるような状態です。
こうした余分なコードのことを「冗長性」と言いますが、なぜ生命はこれほど重複だらけの言葉遣いをするようになったのでしょうか?
実は、この余分に見えるコード(コドン)を整理して、もっとシンプルなものにできないか、というアイデアは以前から注目されていました。
再び言語を例に出せば、日本語の挨拶を全て「こんにちは」にするようにある種の圧縮を行うわけです。
「おはよう」や「こんばんわ」や「やあ」「どうも」などを全て抹消して「挨拶=こんにちは」以外に認めないような圧縮・統一を、全単語に行えば、言語は非常にシンプルになります。
生命も同様で冗長なコードを減らせれば、生命の仕組みをシンプルに理解できるだけでなく、重要な実用的メリットが生まれるからです。
その一つが、ウイルスに感染しにくい細胞をつくることです。
ウイルス(特に細菌に感染するバクテリオファージ)は、自分だけでは増殖できません。
ウイルスは感染した細菌のタンパク質を作る工場を乗っ取り、自分自身を増やすためのタンパク質を作らせます。
ウイルスの遺伝子情報もまた、感染先の細胞と同じ遺伝暗号(コドン)を利用しています。
そこで、細菌側の遺伝暗号からウイルスが利用している特定のコドンをあらかじめ削除してしまえば、ウイルスがタンパク質をうまく作れず、細胞内で増殖できなくなるのです。
ウイルスが日本の機密情報を盗みに来たスパイAIだとするなら、日本語自体を大幅に圧縮・統一してスパイAIが理解できないものにしてしまうのです。
実際に2019年には、ケンブリッジ大学の研究チームが、64種類あるコドンのうち3種類を削除した大腸菌「Syn61」を作り出すことに成功しています。
このとき、Syn61株は多くのウイルスに対して強い耐性を示しました。
ところが後の詳しい研究によって、一部のウイルスはSyn61が削除したコドンを使わなくても感染できる仕組みを持ち込んでいたため、完璧なウイルス耐性とまでは言えないことが判明しました。
つまり、3種類程度のコドン削除では、まだウイルス感染を完全に防ぐことは難しかったのです。
こうした背景から、本研究の研究チームは、これまでよりもはるかに大胆な試みを行うことにしました。
具体的には、これまでのように数種類のコドン削除ではなく、7種類という、これまでにない規模での削減を行いました。
7種類も削ればウイルスが細胞の中で正常にタンパク質を作れる可能性がさらに低くなり、「理論上はどんなウイルス感染にも耐性を持つ細菌」をつくれると期待されたのです。
果たして7種類ものコドンを排除しても生命活動を続けることができたのでしょうか?
10万か所以上の修正で遺伝暗号の根本を削った
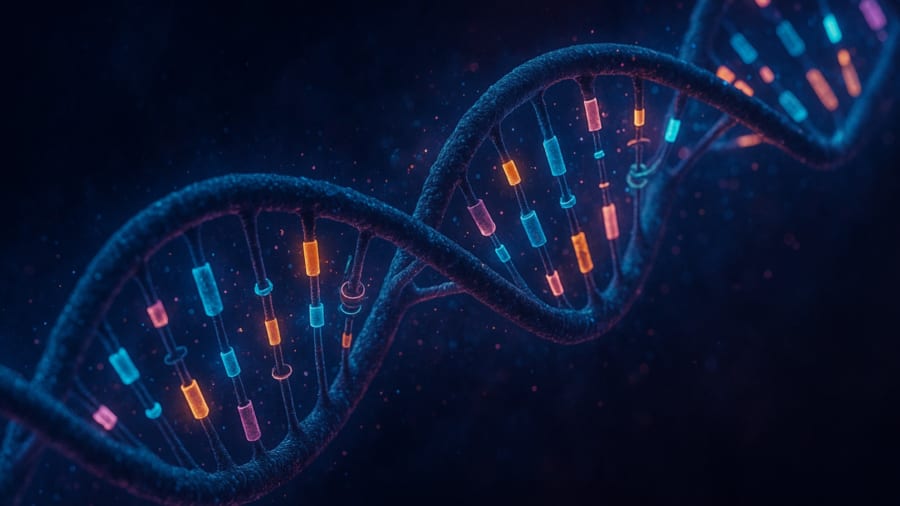
この研究で科学者たちが最初に取り組んだのは、「遺伝暗号の圧縮」が本当に実現可能かどうか、小規模な実験で確かめることでした。
生命が普段使っている64種類の遺伝暗号(コドン)から、まずは限られた領域の中で特定のコドンを削除し、その影響を確かめたのです。
具体的には大腸菌のゲノム(全遺伝情報)から、まずは「セリン」というアミノ酸を指定するコドンのうちの一部と、「アラニン」という別のアミノ酸を指定するコドンの一部、そしてタンパク質の「終止」を指示する特定のコドン(TAGというコドン)の合計7種類を削除し、残る別のコドンで書き換えられるかテストしました。
しかし、実際に生きた細菌のDNAからこれらのコドンを削除するのは簡単ではありませんでした。
というのも、生物のDNAは緻密に設計された建物のようなもので、重要な部分を不用意に取り除くと建物が壊れる可能性があるからです。
そこで研究チームは、いきなり全ゲノムを一度に変更するのではなく、まずはゲノムをいくつかの小さな領域に分け、各領域ごとに設計した通りのコドンの置き換えがうまくいくかを丁寧に検証しました。
その結果、確かにほとんどの領域では計画通りコドンの置き換えが可能でしたが、いくつかの領域では問題が起きました。
重要な遺伝子が並ぶ領域では、コドンを変更すると細菌が正常に成長できないという問題が発生したのです。
この課題を解決するために、研究者たちは新しい工夫を加えました。
問題のある領域の設計を少しずつ変え、どのように変更すれば細菌が正常に成長できるかを徹底的に調べたのです。
例えば、遺伝子の「先頭部分(N末端領域)」は、タンパク質がどれくらいスムーズに作られるかに大きく影響します。
この先頭部分の遺伝情報を注意深く調整しながら、細胞がストレスなく遺伝情報を読み取れるように改良しました。
さらに、遺伝子がオン・オフするスイッチにあたる調節領域(プロモーター)についても慎重に調整を重ねました。
こうした地道な工夫を繰り返すことで、多くの領域で問題が解決できました。
ただ、それでも最終的な目標である約400万個のDNA文字を持つ大腸菌ゲノム全体を一気に書き換えるのは困難でした。
そこで研究チームは「分割して組み立てる」という新しい戦略を取り入れました。
まず大腸菌のゲノム全体を、約100キロ塩基対(kb)ずつの38の断片に細かく分割しました。
各断片でコドンの置換を行い、それぞれの断片を人工的に合成しました。
これらの断片を一つずつ細胞に組み込み、置き換えに問題がある部分を改良しながら、最終的には全ゲノムを統合した一つの人工的な細菌を作り出すことを目指したのです。
ところが、いくつかの断片では、計画通りコドンを置換すると細胞が正常に増殖できないケースが再び現れました。
この問題を解決するために、研究者たちは新たな解析法を考案しました。
具体的には、「連鎖マッピング」という方法を使って、どの領域の変更が細胞の成長を邪魔しているのかを特定しました。
成長が遅くなった細胞と、元の細胞のDNAを比較して問題箇所を探し、そこで改めて置換するコドンの種類を変えるなど、細胞にとって負担の少ない設計に再調整しました。
このような試行錯誤を繰り返した結果、問題となっていた部分の大半が正常な設計に落ち着きました。
こうした改善を何度も積み重ねながら、38個の断片を徐々に統合し、最終的に人工ゲノムを一つの完全な大腸菌ゲノムとして組み立てることに成功しました。
出来上がった人工細菌は「Syn57」と名付けられました。
その名前が示す通り、この細菌は通常64種類あるコドンのうち7種類を削減し、57種類だけのコドンで生命活動を維持できるようになっていました。
このSyn57株では、約10万1千箇所のDNAの変更が必要でしたが、最終的に予定した変更の99.9%を達成しました。
また驚くべきことに、この人工細菌は遺伝子の変更にもかかわらず、実験室環境でゆっくりですが安定して増殖を続けることが確認されました。
こうして完成したSyn57は、「コドンを大幅に削減しても生物が生存可能である」ことを初めて明確に証明した、画期的な成果となりました。
研究者たちは、この成果によって「理論上ほぼ全てのウイルスに対して強い耐性を示す」細菌を作り出せる道が開かれたとしています。
ただし、実際に全てのウイルスへの耐性が証明されたわけではなく、今後のさらなる検証が必要です。
また、この研究は単にウイルス耐性だけにとどまらず、新たな人工タンパク質やバイオポリマーの生産といった、未来の技術開発のための基盤となる可能性も秘めています。
つまり、この研究が示した技術を土台として、これまでの自然界にはない、新しい可能性を秘めた生物を設計する時代が現実に近づいたのです。
【まとめ】人工的に設計された生命「Syn57」は世界をどう変えるか?
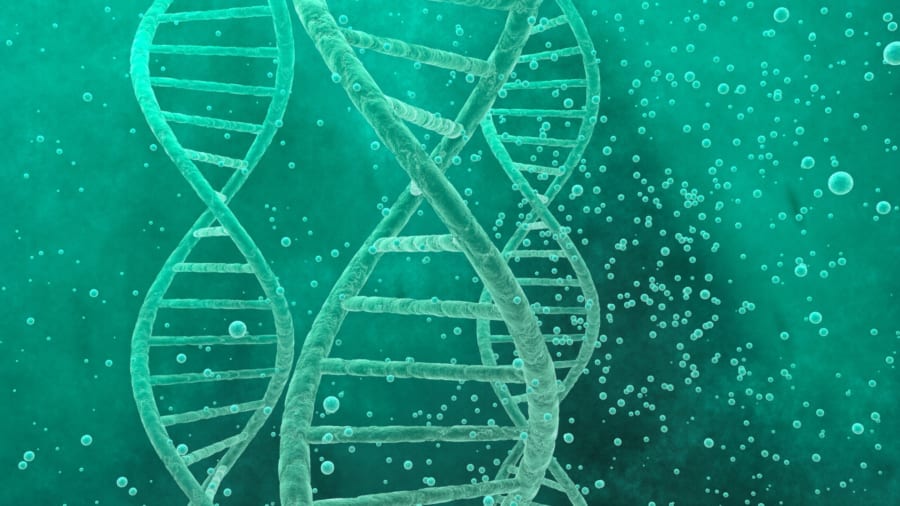
今回の研究によって、「生命が使う遺伝暗号(コドン)は私たちが考えていた以上に自由に書き換え可能であること」が初めて明確に示されました。
これまで、生命の遺伝暗号は64種類のコドンがあり、それらが20種類のアミノ酸を指定することでタンパク質が作られていることが知られていました。
そして、もしこの遺伝暗号から一つでもコドンを取り除けば、生命活動に致命的な影響を与えると長い間考えられてきました。
なぜなら、遺伝暗号は地球上で数十億年もの進化の中で培われてきたものであり、それほど重要なコードを大きく変更することは生命にとって不可能に近い挑戦だと思われていたからです。
ところが、今回の実験で科学者たちは、なんと7種類ものコドン(これは全体の約1割に相当します)を一気に削除した遺伝暗号を持つ人工大腸菌「Syn57」を作り出すことに成功しました。
この人工細菌は遺伝情報を大きく変更したにもかかわらず、実際に生命活動を続け、細胞分裂によって子孫を残すこともできました。
つまり、私たちが想像していたよりも生命はずっと柔軟で、遺伝暗号の一部を大胆に取り除いても、生きていくための基本的な機能は維持できることが分かったのです。
この結果を理解するために、日本語の文章で例えてみましょう。
似たような意味を持つあらゆる単語を圧縮して統一すると効率が悪く、読みにくくなりますが、それでも意味が通じる文章を書くことは可能です。
同じように、今回の実験で人工大腸菌のDNAからいくつかのコドンを削除したことで、細菌は以前よりも少し「読みづらい」状態になりました。
そのため細菌の成長速度が遅くなりましたが、生命活動自体はしっかり維持されました。
つまり生命の遺伝暗号は、多少の非効率さを許容できる余裕があったということです。
では、そもそもなぜ自然の進化は、このような一見非効率な「冗長な遺伝コード」を維持してきたのでしょうか。
研究者たちは、コドンがいくつも重複していることで、タンパク質を作る速度を微妙に調節したり、あるいは突然変異が起きても致命的なダメージを受けない安全策として働いている可能性を指摘しています。
遺伝子には「タンパク質の作り方」だけでなく、「どのタイミングでどのくらい作るか」という調節情報も含まれています。
複数のコドンを使い分けることで、タンパク質合成の速度や精度を微妙に調整しています。
これを1つのコドンに統一してしまうと、タンパク質を作るスピードや量の微調整が難しくなり、細胞にとって負担になる可能性があります。
また複数のコドンで同じアミノ酸を指定しているおかげで、DNAにちょっとしたミス(突然変異)が起こっても、被ったコドンのお陰で同じアミノ酸(材料)が指定されれば、タンパク質が変化しないで済むことがあります。
逆にコドンを1つのみに絞ってしまうと、わずかなミスでも致命的な問題が起きる可能性が高くなり、生物の生存率が大幅に下がる恐れがあります。
つまり、生命は冗長な遺伝コードを「無駄」としてではなく、「安全装置」として利用してきた可能性があるのです。
そのため、冗長性を削減した細菌は成長速度がやや低下しましたが、それでもこの実験は生命が遺伝コードの単純化に十分耐えられることを証明しました。
さらに今回の研究の重要なポイントは、遺伝暗号を圧縮することが「ウイルスに感染されにくい細菌」を作り出す新たな道を開いたことです。
細菌に感染するウイルスは通常、細菌が持つ遺伝暗号を使って自分自身を複製します。
今回のように、細菌側でウイルスが使うコドンをあらかじめ削除しておくと、ウイルスは正常にタンパク質を作れなくなり、理論的には細胞内で増殖できません。
つまりコドンの削減は細菌にとって「遺伝的ファイアウォール」のような働きをするのです。
もちろん、まだ完全なウイルス耐性を実証したわけではありません。
過去の研究でコドンを減らした細菌でも、ウイルスが別の方法で細菌に感染した例が報告されています。
しかし研究チームは、将来的にさらに高度な技術を組み合わせることで、ほぼ完璧なウイルス耐性細菌を作り出せる可能性があると考えています。
例えば、今回空いたコドンのスペースに「自然界にない新たなアミノ酸」を人工的に割り当てれば、ウイルスが簡単には対応できない、より強固な耐性が得られる可能性があります。
実際、別の研究グループは削減されたコドンをあえて別のアミノ酸に置き換えて、ウイルスがタンパク質を正しく作れないようにする新しい方法も報告しています。
こうした複数の戦略を組み合わせれば、「極めてウイルスに感染されにくい細菌」が実用化される日が近づいています。
【コラム】ウイルス感染に完全耐性を持つ細菌は爆発的に増加したりしないのか?
今回の研究で作られた人工細菌「Syn57」は、遺伝暗号を大幅に削減することで、理論上、ほぼすべてのウイルスに対する強力な耐性を持つことが期待されています。しかし、このように「ウイルスに感染されない細菌」を作り出すことには、倫理的・生態学的な懸念やリスクも議論されています。まず懸念されるのが、ウイルスに感染されない細菌が環境中で「爆発的に増殖してしまうのではないか?」という点です。細菌とそれを攻撃するウイルスは、生態系の中で自然にバランスを取りながら共存しています。ウイルスが細菌の個体数を一定程度抑制することで、ある種の細菌が過剰に増殖するのを防ぎ、生態系の多様性を保つ役割を果たしています。ところが、もし完全にウイルス耐性を持つ細菌が自然界に放出された場合、その細菌を抑制するメカニズムが一つ失われることになり、細菌が異常に繁殖して生態系のバランスが崩れる可能性があります。実際、今回の研究を行った英国MRC分子生物学研究所(MRC-LMB)をはじめ、世界各地の研究機関の科学者たちは、このリスクを真剣に受け止めています。プレスリリースなどで研究チームは、「ウイルス耐性細菌が環境に与える影響を徹底的に調査・評価する必要がある」と明言しています。ただ今回の研究のような人工生物が現状すぐに環境中で爆発的に増殖する可能性は極めて低いと考えられています。先に述べたように実際に作り出された人工細菌は自然な大腸菌よりも増殖速度が遅く、環境中では生存競争に負けやすい可能性が高いと報告しています。つまり、人工的に変更された遺伝暗号を持つことは、細菌の生存にむしろ「負担」となり、環境中で爆発的に増殖するリスクは現時点ではそれほど高くないと考えられているのです。
さらに今回の研究成果は、バイオテクノロジーや医学の分野でも大きな可能性を秘めています。
たとえば、医薬品を作る工場では細菌に感染するウイルス(ファージ)の汚染で製造ラインが止まってしまうことがありますが、今回の技術で作られた耐性細菌を使えばそのリスクを大きく減らせます。
また遺伝暗号を独自のものに書き換えた細菌は、環境中に万が一放出されても周囲の自然な細菌と遺伝情報をやり取りできないため、遺伝子汚染のリスクが小さくなります。
これは汚染物質の分解や難治性疾患の治療など、様々な場面で安全に人工的な生物を活用するための重要な基盤となります。
最後に、本研究の最も重要な意義は「人工的な遺伝子設計の時代を本格的に切り開いた」ことにあります。
自然の進化では決して到達できなかった生命の新たな可能性を、人間がゼロからデザインし、実際に生きた細菌として作り出すことが現実になったのです。
将来的には、今回作成したSyn57を土台に、これまで自然界になかった新しいタンパク質や素材を作り出したり、新しい医療技術の開発に利用したりすることが可能になります。
もちろん倫理的・安全面の議論はこれからも必要ですが、今回の研究は私たちが生命の遺伝暗号を書き換え、新たな可能性を持つ人工生物を自在に設計する未来に向けた、記念すべき大きな一歩と言えるでしょう。
また、コドンを削除することにはもう一つ、大きな利点があります。
それは「削除によって空いたスペースを新たな目的に使える」ということです。
今まで余分だったコドンを「人工的なアミノ酸」を指定するためのコードとして再利用できるのです。
こうすることで、自然界には存在しない新しいタンパク質やポリマー素材を人工的に作れるようになります。
例えば、薬や化粧品の原料となる複雑なタンパク質を、自然界の20種類のアミノ酸だけで作るのは難しい場合がありますが、人工的なアミノ酸を組み込めれば、全く新しい機能を持つ分子を生み出せます。
さらに人工的な遺伝暗号を使う生物は、自然界の生物と遺伝情報を交換することが極めて難しくなります。
つまり、万が一人工生物が環境中に漏れ出しても、周囲の生態系に遺伝子が広がる危険性(遺伝子汚染)を防ぐことが可能になるのです。
このように、人工的に再設計された遺伝暗号は、医薬品開発やバイオ素材製造といった産業利用だけでなく、環境安全性という点でも非常に大きなメリットがあります。
しかし、そのような応用を実現する前に、そもそも生命がどの程度までコドンを減らすことに耐えられるのかを確かめることが重要です。
本研究の最大の目的は、これまでの3種類よりもさらに多くのコドンを削減しても、本当に生命活動が維持できるのかを探ることだったのです。
元論文
Escherichia coli with a 57-codon genetic code
https://doi.org/10.1126/science.ady4368
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


