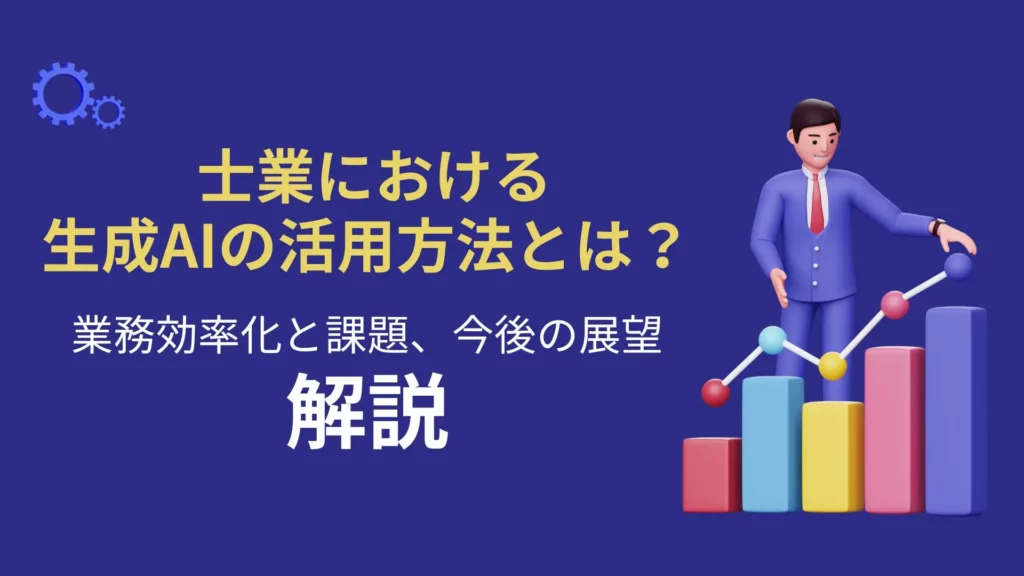
- 業務を効率化したい士業の方
- ChatGPTなど生成AIを使いこなしたい方
- 生成AIに仕事をとられたくない方
ChatGPTをはじめとする生成AIの進化により、ビジネスの現場では業務の効率化が進んでいます。その影響は、法律や税務などの専門分野を担う「士業」にも及びはじめました。
契約書の作成や調査、リサーチ、説明資料の作成など、日々の業務に生成AIを取り入れることで、作業時間の短縮や品質の向上が実現しつつあります。一方で、AIの活用によって業務内容や役割そのものが見直される局面も出てきています。
この記事では、士業と生成AIの関わり方や活用場面、今後の課題と展望について、わかりやすく解説します。
士業における生成AI
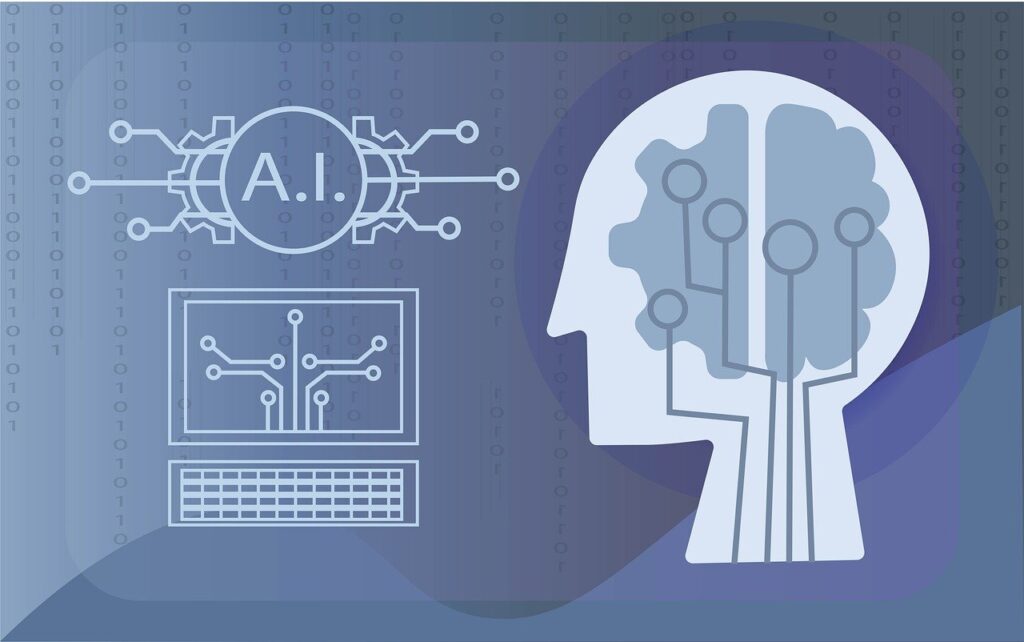
「士業(しぎょう)」とは、特定の国家資格を持ち、専門知識や技能を活かして、他者にサービスを提供する職業を指します。多くの場合、資格を取得した上で登録をしなければ名乗れず、独占業務(資格を持つ人だけができる仕事)が法律で定められていることが特徴です。「 ︎
︎ ︎士」とつくことが多いため、まとめて「士業」と呼ばれています。
︎士」とつくことが多いため、まとめて「士業」と呼ばれています。
士業における生成AIの関わりとしては、契約書や申請書類のドラフト作成、調査の効率化、FAQや記事の作成補助などに活用され、業務負担を軽減する動きが広がっています。
生成AI時代の士業が抱える共通の課題
近年、生成AIは日々進化を続けています。こうした時代の中で、士業が共通して抱える課題として、主に2つの点が挙げられます。
生成AIスキルによる格差
生成AIを使いこなせる士業と、使いこなせない士業の間で、格差が生まれつつあります。
AIを活用できる士業は、契約書のたたき台作成や調査業務の時間短縮が可能になり、より多くの案件をこなしたり、付加価値の高い業務に注力したりできるようになりました。
一方、AIを使いこなせない士業は、従来通りすべて手作業で対応するため、スピード・コスト面で競争力を失うリスクが高まっています。
生成AIはあくまで補助ツールであるものの、使い方次第で仕事の生産性やクオリティに大きな差がつく時代になっていると言えるでしょう。
生成AI普及による需要低下
生成AIの普及により、士業への依頼件数そのものが減る可能性も指摘されています。
簡単な契約書や申請書の作成であれば、士業に依頼しなくてもAIツールを利用することで自力での対応が可能です。特に、定型的でリスクが低い業務は「無料または低価格なAIサービス」で済まされることが増えるでしょう。
これからの士業には、単純作業ではない「付加価値の高い専門アドバイス」や「リスク回避を含む伴走支援」など、AIでは代替できない強みを打ち出すことが求められます。
なお、業務効率化のための生成AI活用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
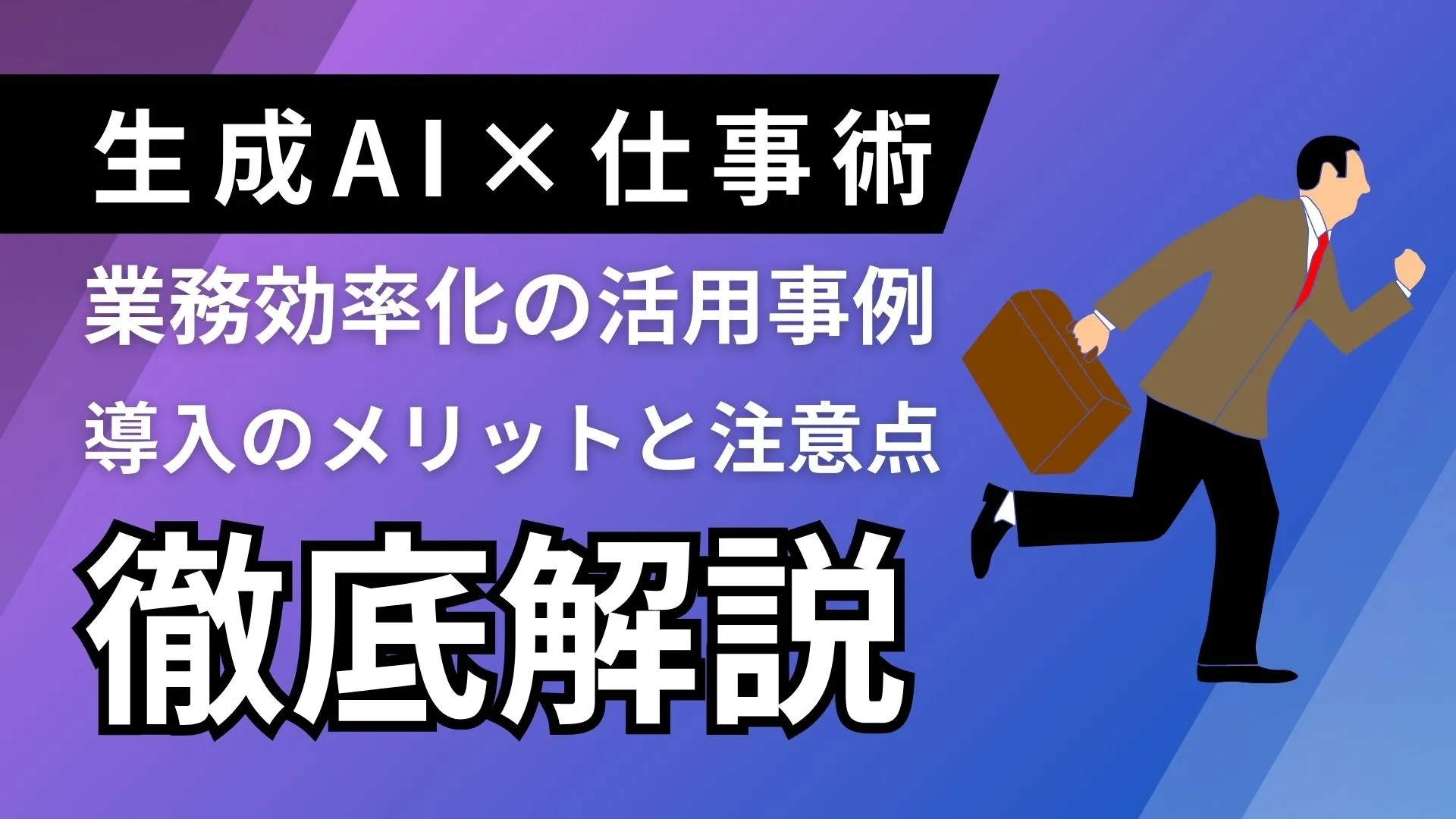
士業における生成AIの活用シーン
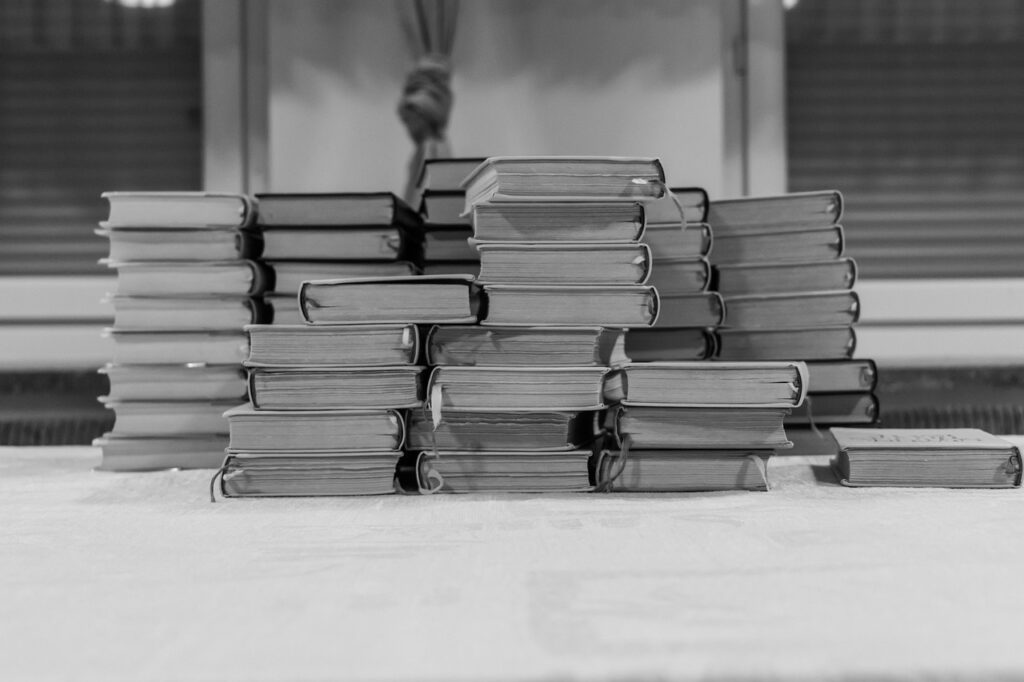
士業においても生成AIを活用することで業務時間の短縮が可能です。実際にどのような場面で活用できるか解説していきます。
文書の要約
士業の現場では、契約書、判例、条文解説など膨大な文書を扱います。生成AIではこれらの長文資料を短時間で要約し、要点を整理することが可能です。
たとえば、契約書の要点を抜き出してクライアント向けに簡潔にまとめる、裁判例の要旨をピックアップする、といった作業がAIにより効率化できます。これにより、士業本人は文書全体に目を通さなくても重要ポイントを素早く把握でき、判断や対応のスピードが上がるでしょう。
文書から必要な情報の抽出
士業の仕事では、数十ページにも及ぶ契約書や資料から特定の情報を抜き出す作業が日常的に発生します。生成AIを活用すれば、「特定条項だけを一覧化」「日付や金額などの数値データを抽出」といった作業を自動で行うことが可能です。これにより、手作業によるミスを防ぎながら、大幅な時間短縮が実現できます。
特に大量の案件を処理する必要がある士業にとって、AIによる情報抽出は作業効率を劇的に向上させる強力な武器といえるでしょう。
検索・リサーチ
士業の業務には、法改正情報、最新判例、専門知識のリサーチが欠かせません。生成AIは、膨大なデータベースから必要な情報を瞬時に検索し、要点をまとめて提示することができます。
たとえば、「このケースに関連する過去の判例は?」「最新の税制改正点は?」といった質問にも短時間で回答を得ることが可能です。従来は膨大な時間をかけていたリサーチ業務が効率化され、士業はより本質的な問題解決やクライアント対応に時間を割けるようになります。
過去の事例に基づく判断の自動化
士業の判断業務では、過去の類似事例に基づいて適切な対応策を選ぶ場面が多くあります。生成AIは過去の判例や処理実績データを分析し、似たケースに対する判断パターンを提案することが可能です。
たとえば、特定の契約違反に対して過去どのような損害賠償が認められたか、過去の税務調査で問題になったポイントは何か、といった情報をAIが整理し、参考材料として提示します。これにより、士業の判断をサポートし、より迅速かつ適切な対応が可能になるでしょう。
なお、法務業務における生成AI活用について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
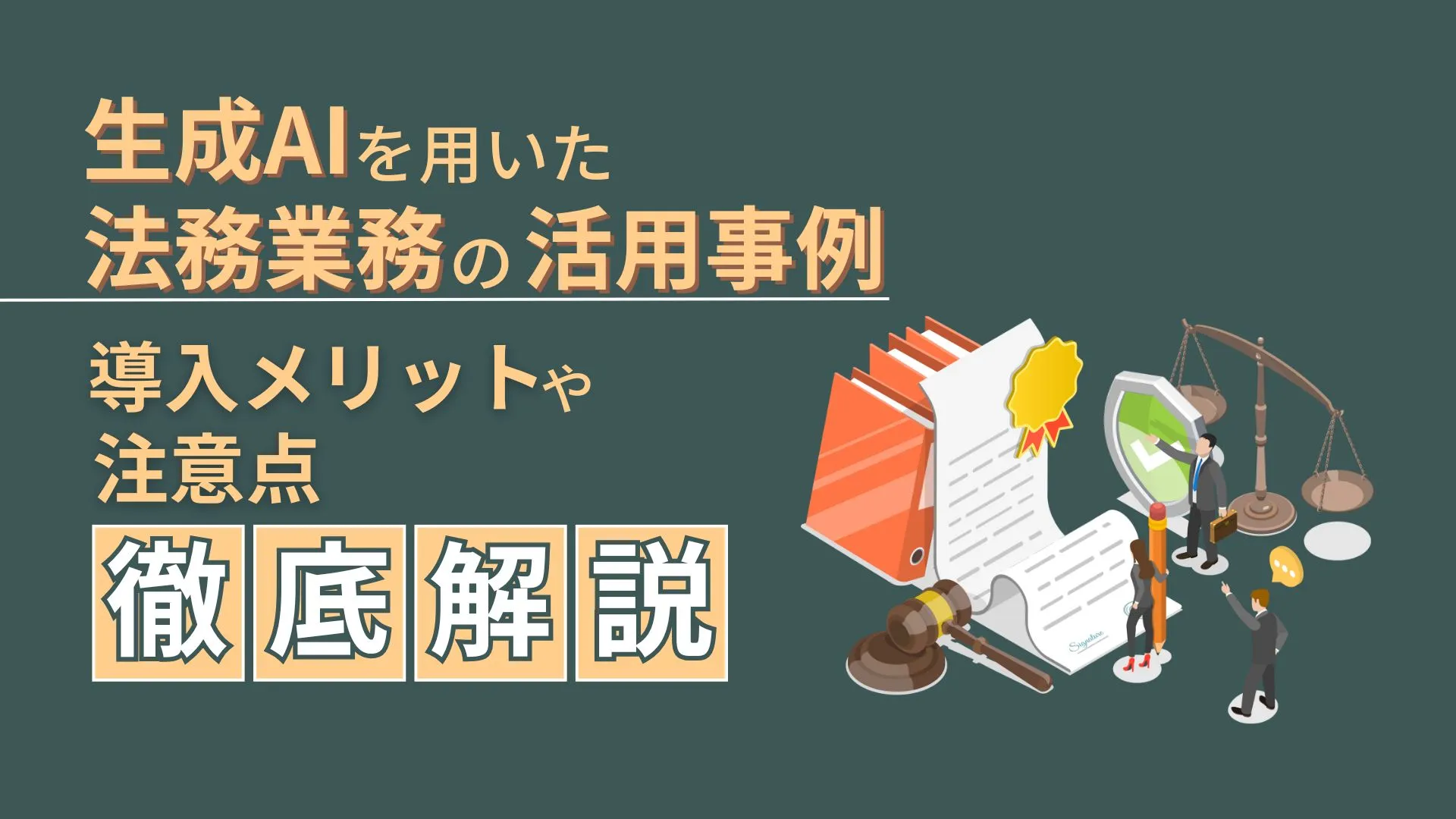
各士業で生成AIが活躍できる場面
前の章では士業全体での活用方法をご紹介しました。ここでは具体的に、各士業で生成AIが活躍する場面をご紹介します。
弁護士
生成AIは契約書のドラフト作成、法令検索、過去の判例要約などに活用可能です。依頼者からの初期相談に対する仮回答の作成や、社内のナレッジ整理、FAQ対応の効率化にも役立ちます。業務負担が大きい調査業務をAIで時短できるため、より戦略的な法務判断に集中する時間を確保できるでしょう。
司法書士
司法書士の場合、不動産登記や商業登記に関する書類作成の自動化が期待できます。定型的な文書の下書きをAIに任せ、法的要件を満たしているかの確認を専門家が行うことで、業務効率が向上するでしょう。また、依頼者に向けた解説資料や手続きフローの生成にもAIが活用可能です。
弁理士
弁理士においては特許明細書のドラフト作成や、類似特許の検索・要約にAIが力を発揮します。専門性の高い文書の整理や、出願前の技術情報のリサーチを支援し、短期間でより多くの案件に対応できるようになります。また、外国語文献の翻訳や要約にも活用が可能です。
税理士
税務申告書類のドラフト作成、税法改正の要点整理、顧問先への説明資料の自動生成などでAIが活躍します。質問対応のテンプレート化や、過去の顧客データをもとにした節税提案なども、AIの力を借りることで効率的に行えるようになるでしょう。
社会保険労務士
労務管理に関する書類の作成や、就業規則のひな形作成、労働関連法令の変更点の要約にAIを活用可能です。企業ごとにカスタマイズしたアドバイス文書や説明資料を素早く生成できるため、相談対応や顧問業務の効率が大幅に向上します。
行政書士
許認可申請書類のドラフト作成、添付書類リストの整理、業務フローの図解化などでAIが活用されます。依頼者への説明資料やよくある質問への回答作成もAIが得意とする領域です。特に多様な業種の手続きに対応する行政書士にとって、情報収集力の補完として活躍が期待できます。
土地家屋調査士
図面作成自体は専門ソフトを使用しますが、調査報告書の要約、説明文の作成、依頼者への通知文などの文書業務で生成AIが活躍します。また、過去の調査事例を分類・整理し、ナレッジベースとして活用することで業務効率化が可能です。
海事代理士
複雑な海事関係の法令・手続きの要点整理や、外国語資料の翻訳・要約に生成AIが役立ちます。依頼者への提出書類や説明文のドラフト作成、船舶登録に伴う文書テンプレートの整備などもAIにより効率化され、正確性とスピードが向上するでしょう。
公認会計士
会計監査に必要な手続き書類の要約や、会計基準の比較資料作成、分析コメントのドラフト作成などに生成AIが活用可能です。膨大な財務データから特定傾向を抽出したり、クライアントごとのレポートを自動化することで、監査業務の生産性が高まります。
中小企業診断士
事業計画書やSWOT分析レポートの作成支援、ヒアリング内容の要点整理、提案資料の作成補助などでAIの活用が可能です。幅広い業種の相談に対応するための情報収集や、業界動向の要約なども、AIの検索・分析能力が大きな助けになります。
不動産鑑定士
鑑定評価書の補足資料作成や、不動産市場動向の分析要約、顧客向け報告書の下書き作成にAIが使われます。過去の評価事例との比較レポートを自動生成したり、物件の周辺環境データの収集を効率化したりすることで、業務全体の精度とスピードが向上するでしょう。
生成AI時代の士業はどうなる?
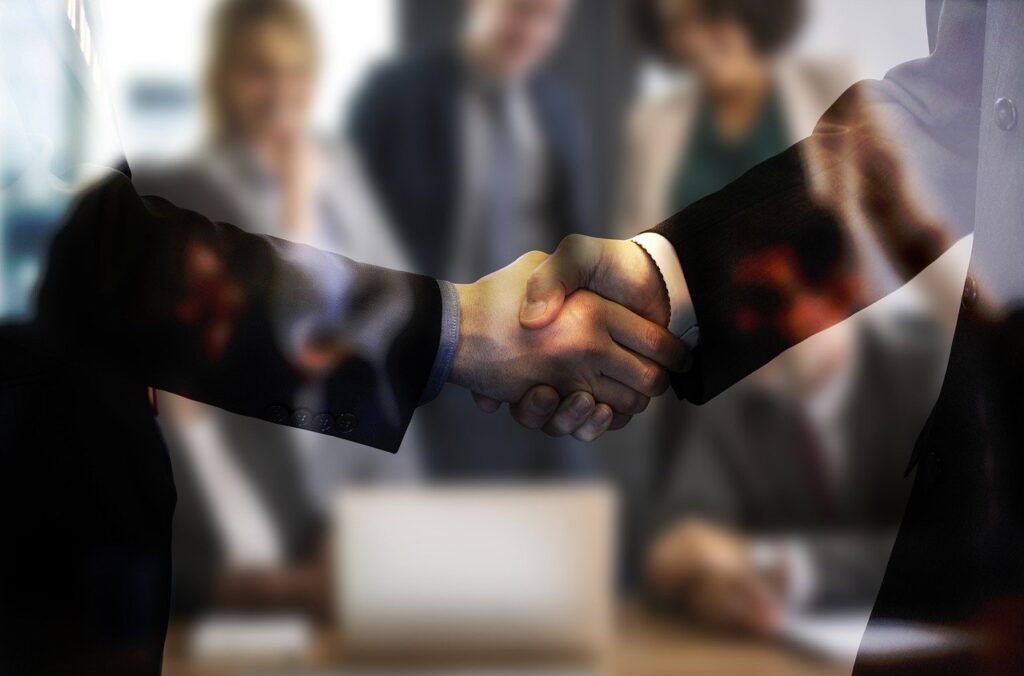
生成AIの登場で士業の業務は大きく変わりつつあります。文書作成や調査業務はAIが担うようになり、効率化とスピードアップが進んでいます。
一方で、依頼者の真意を汲み取る力や、複雑な判断・責任の所在といった本質的な部分は変わりません。AI時代の士業には「生成AIを使いこなす力」と「人間だからできる価値」の両立が求められます。
なお、生成AIによって仕事がどのように変化するのかについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
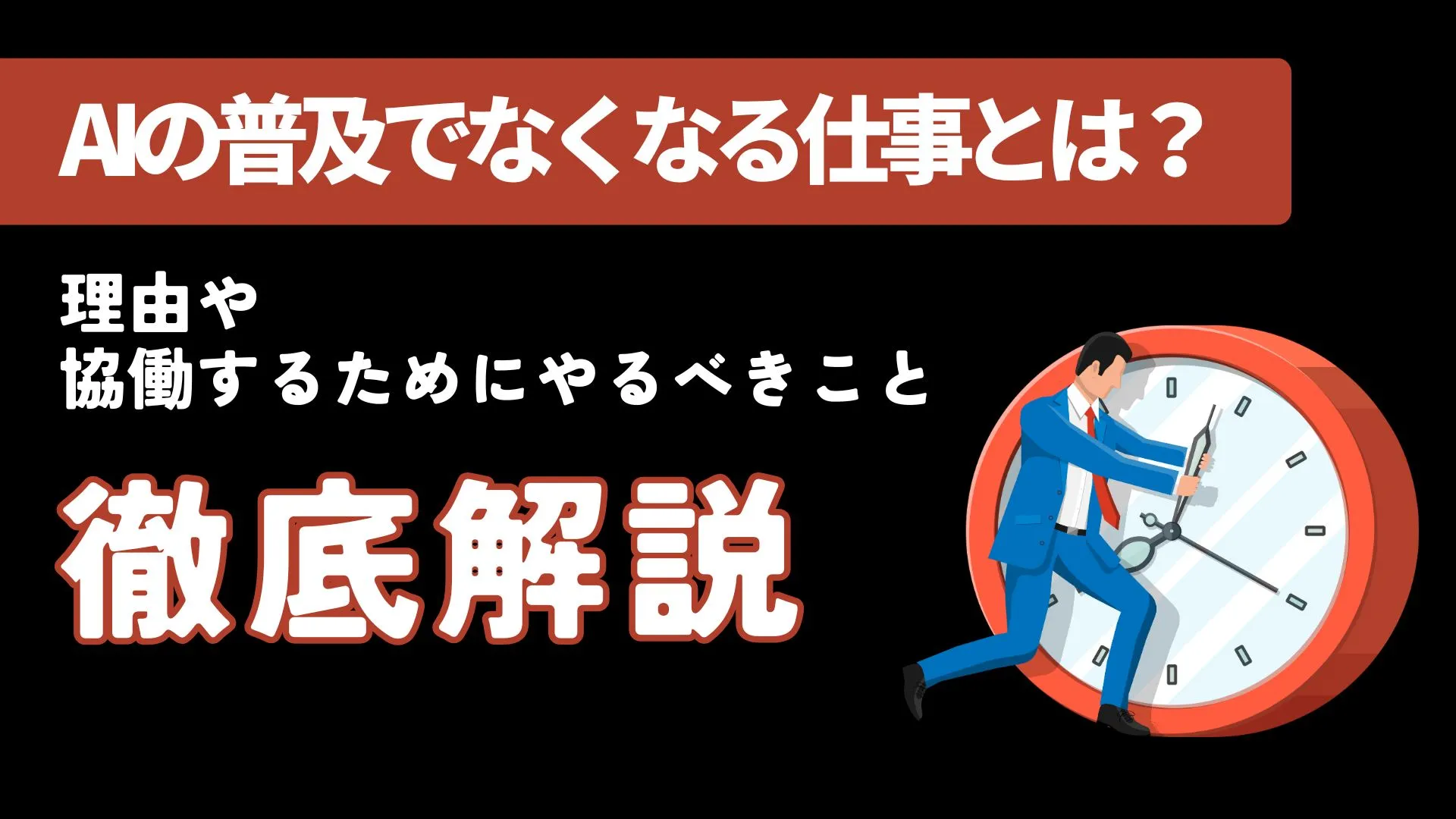
生成AIは士業の分野でも活躍!
今回は生成AIがどのように士業の分野で活用できるかを解説しました。
生成AIは、士業にとって単なる業務効率化ツールではなく、「どう使うか」で成果が大きく変わります。単純作業はAIに任せ、士業はより高度な判断や信頼関係構築など、人間にしかできない領域に注力することが求められるでしょう。
AIの台頭により依頼件数が減る可能性もありますが、それを恐れるのではなく、強みの再定義と差別化のチャンスと捉えることが重要です。生成AI時代において、士業が選ばれ続けるためには、「専門性」と「AI活用力」の両輪を育てていく姿勢が鍵になります。
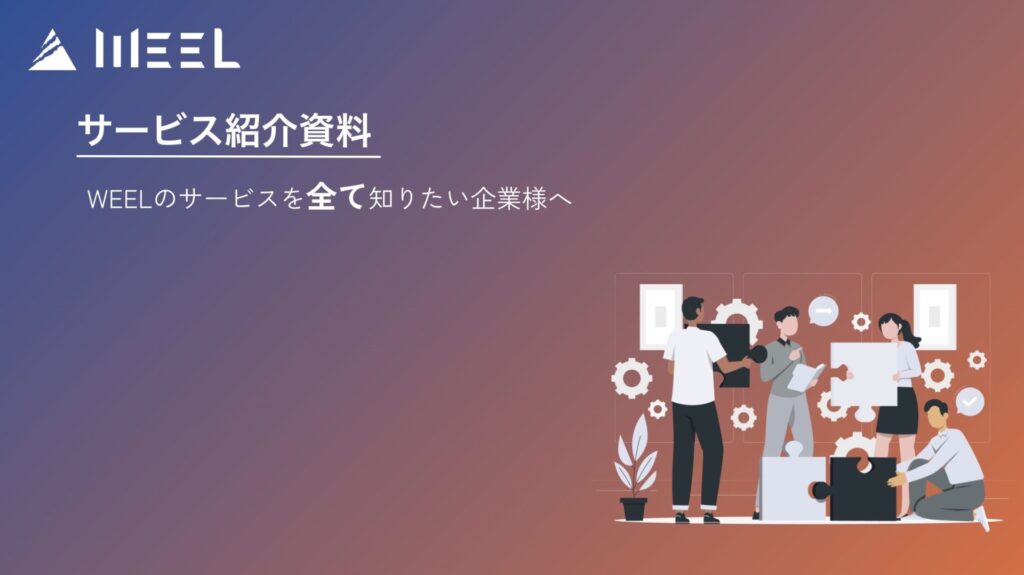
生成系AIの業務活用なら!
・生成系AIを活用したPoC開発
・生成系AIのコンサルティング
・システム間API連携
最後に
いかがだったでしょうか?
生成AIの導入は、士業の業務効率だけでなく、サービス提供のあり方そのものを変え始めています。実務に即したユースケースを踏まえ、自社の強みを活かしながらAIをどう取り入れるべきか、具体的な視点で整理してみませんか?
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの執行役員として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。
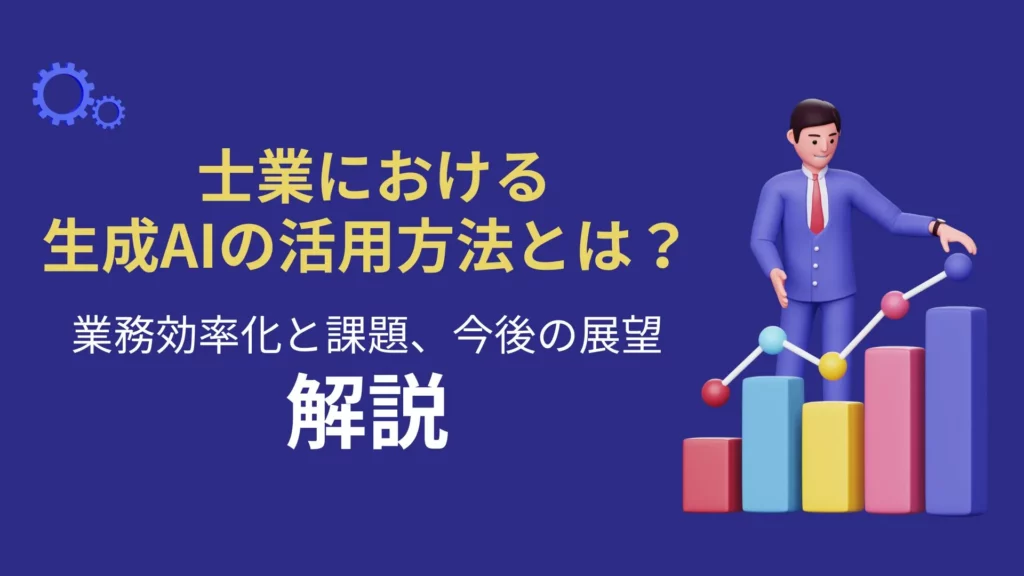
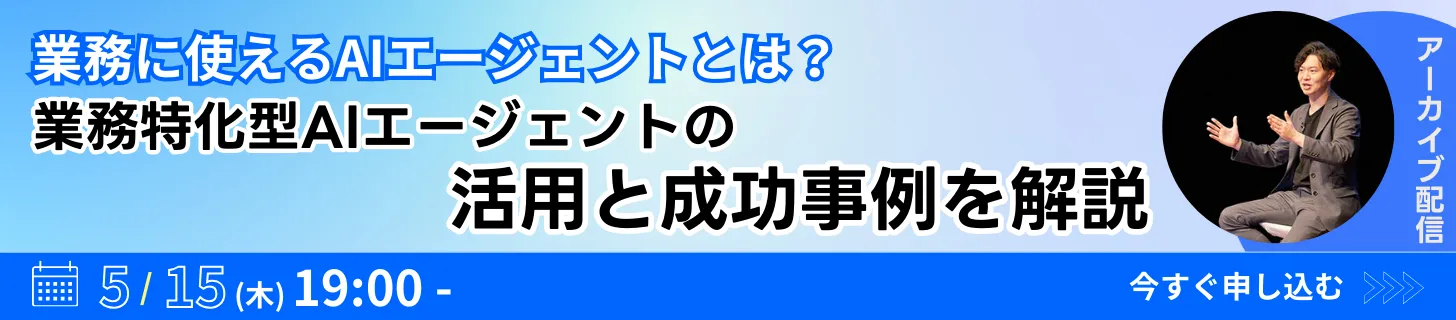
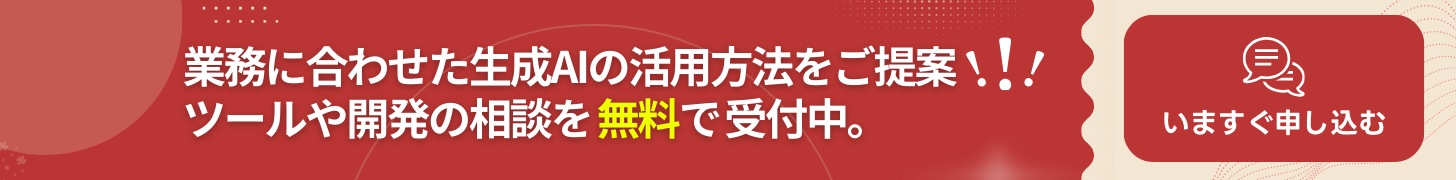
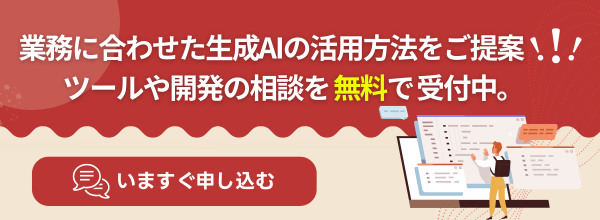
 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。
︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。
