オーストリアのインスブルック大学(University of Innsbruck)で行われた研究によって、特定の条件下では「物に力を加え続ければ必ず熱くなり乱雑さが増加する」という常識が、量子の世界では当てはまらないことが実験で示されました。
研究では極限まで冷やした原子集団に繰り返し外部からの力を加えたとき、運動エネルギーEと情報エントロピーSが調べられており、それらが数百回のキックで頭打ちになりることが確認されました。
このように外部から衝撃を与えても加熱が進まず、エネルギーと乱雑さが飽和する量子ガスの振る舞いは、古典物理学で予想される「エネルギーの拡散や乱雑さが増え続ける」直感に反するものです。
いったいなぜ原子たちはこれ以上エネルギーを吸収せず、まとまりを保てたのでしょうか?
研究の詳細は2025年8月14日に『Science』にて掲載されました。
目次
- エントロピーと熱の常識に量子が反乱を起こすのか?
- 量子は常識に抗い、加熱は頭打ち
- 熱化を制御する未来──量子技術へのヒント
エントロピーと熱の常識に量子が反乱を起こすのか?

私たちの身近な世界では、「熱」はとても当たり前の現象です。
たとえば、両手をこすれば温かくなり、金属を何度も叩くと熱を帯びます。
これは「エネルギーを加えると物体が熱くなり、整った状態がだんだん乱れていく」という自然な流れです。
この「乱れ」を表す物理の基本概念がエントロピーです。
簡単にいえば、「中の粒子がどれだけバラバラで自由に動いているか」を示す指標です。
熱力学では「閉じた系ではエントロピーは必ず増える(乱雑さが増す)」という熱力学第二法則が成り立ちます。
この法則は、原子や分子のような小さな粒子の世界でも成り立つと長く考えられてきました。
特に多くの粒子が強く相互作用している場合は、エネルギー交換が活発になり、より早く熱が広がると予想されていました。
しかし、量子力学のルールが支配する世界では事情が変わります。
粒子は波としての性質を持ち、波どうしは「干渉」します。
この干渉によって粒子の動きが特定の範囲にとどまり、エネルギーが思ったほど広がらないことがあります。
こうした量子のまとまり(コヒーレンス)や干渉が働くと、外からエネルギーを加えてもある時点でそれ以上吸収しなくなる現象が起こります。
これを動的局在(ダイナミカル・ローカリゼーション, DL)と呼びます。
たとえば「量子キックローター(QKR)」というモデルでは、一定間隔で外力(キック)を加え続けても、運動量の広がりが止まることが理論と実験で確かめられています。
この現象は、電子が無秩序な環境で動けなくなる「アンダーソン局在」にも似ています。
ただし、これまで詳しく分かっていたのは粒子どうしの相互作用がほとんどない場合でした。
現実の物質では粒子は互いに影響し合い、この相互作用によってコヒーレンスが乱れ、結局は熱化してしまうと長く考えられてきました。
今回の研究は、「強く相互作用する多数の原子でも、条件次第でエネルギーの広がりや乱雑さの増加を抑えられるのか」という疑問に挑みました。
量子のまとまりがどこまで保たれるのか、そして量子の秩序が古典的なカオスへと移行する境界を実験で明らかにすることを目指しました。
量子は常識に抗い、加熱は頭打ち

今回の実験は、現代物理学の中でも特に精密な研究のひとつに数えられます。
まず研究チームは、セシウム原子を約2ナノケルビンという、ほとんど絶対零度(−273 ℃)に近い温度まで冷やしました。
すると、原子たちは「ボース気体」と呼ばれる状態になり、多数の原子がまるでひとつの巨大な波のように振る舞う特徴が現れます。
さらにチームは、磁場を使って原子同士がどれくらい押し合うか(相互作用の強さ:γ)を調整できるようにし、原子を細長い一次元チューブ(前後の方向にしか動けない空間)に並べました。
次に、この一次元の原子列に対して、縦方向にレーザー光を使って光の縞模様(光格子)を作り、それを短時間だけ点けたり消したりすることで、「キック」と呼ばれる力を周期的に加えました。
普通であれば、何度も力を加えられた原子たちはどんどん速く動き始め、運動エネルギーE(吸収されたエネルギーの目安)や、運動の広がりを表す情報エントロピーSが増え続け、結果として「熱化」が進むと予想されます。
ところが今回の実験では、数百回のキックの後に運動エネルギーEと情報エントロピーSの増加が止まり、どちらも一定の値で安定(飽和)するという予想外の現象が観測されました。
それだけでなく、原子の運動量分布n(k)の変化の度合いを測る指標であるJensen–Shannon距離Jもノイズと区別がつかないほど低下しました。
これは、原子の運動状態がほとんど変わらなくなったことを意味します。
つまり、どれだけ原子同士が強く押し合っていても、外からの駆動によってエネルギーがどんどん拡散していくのではなく、ある状態で“凍りついた”ように保たれていたのです。
この現象は、多体系動的局在(MBDL)と呼ばれ、理論では予想されていたものの、今回の実験によって初めて明確に確認されました。
さらに論文では、この局在状態がどれほど安定しているかを調べるため、理論モデルを使って「キックのタイミングにランダムなズレ」を加えた場合のシミュレーションが行われました。
その結果、今度は運動エネルギーEと情報エントロピーSはキックを繰り返すたびに増え続けてしまいました。
つまり、エネルギーは再びどんどん拡散し、系は熱化するようになったのです。
この結果からわかるのは、外から加える力がきちんと一定のリズムであることが、量子の波のまとまり(コヒーレンス)を維持するためにとても重要であり、ほんの少しでもそのリズムが崩れると、原子たちはたちまちバラバラに動き出してしまうということです。
研究チームは、これらの結果を受けて「量子コヒーレンスと強い相互作用の組み合わせこそが局在状態を保つためのカギになる」と結論づけています。
外部からの駆動がしっかり整っていれば秩序が保たれ、少しでも乱れると一気に秩序が壊れてしまう――この極端な“敏感さ”こそが、量子の世界ならではの特性だといえるでしょう。
熱化を制御する未来──量子技術へのヒント
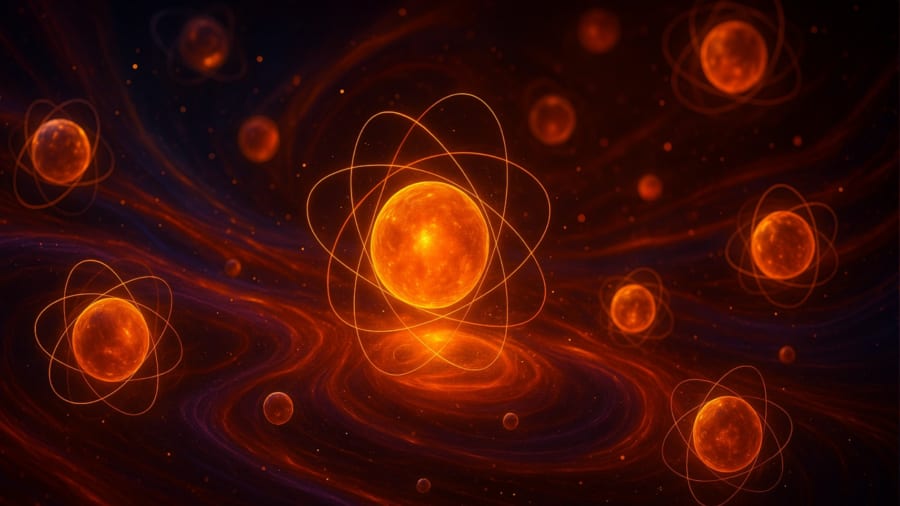
今回の研究が示したもっとも重要な成果は、「強く押し合う多数の原子が集まった量子の世界で、何度も規則正しく力を加えても、運動エネルギーEと情報エントロピーSが途中で増えなくなり、安定したまま保たれる」という現象を、実際の実験で確認できたという点です。
ふつうであれば、粒子に繰り返しエネルギーを与えると、動きはどんどんバラバラになり、エネルギーもまわりに広がっていきます。
これは、私たちの目に見える世界(=古典的な物理の世界)ではごく自然なこととされています。
ところが今回のように、粒子が「波」として振るまい、その波同士がきれいに重なり合う性質(コヒーレンス)が強く働く量子の世界では、状況が変わってきます。
今回の実験では、エントロピーSは最初のうちは増えますが、ある時点でピタリと増加が止まり、その後は一定のまま保たれるという現象が確認されました。
ここで大切なのは、「エントロピーが減った」のではなく、「増え続けるのをやめて、止まったままになった」という点です。
つまり、熱の吸収を完全に拒んだわけではなく、「少し乱れた状態のまま、それ以上変わらない」というバランスのとれた状態が保たれていたのです。
この特別な状態が成立するのは、量子コヒーレンスと原子同士の強い押し合い(相互作用)がちょうどよく釣り合っていたからだと考えられます。
しかし、このバランスは非常に繊細です。
たとえば、外からの力のタイミングにランダムなズレ(予測できない乱れ)を加えてみると、せっかく保たれていた状態はすぐに壊れてしまいました。
その結果、エントロピーSや運動エネルギーEは止まることなく増え続け、粒子の動きは再び広がり始め、古典的な熱化と拡散の状態に戻ってしまったのです。
このことから、量子コヒーレンスと相互作用の組み合わせが、局在状態(動きが止まった状態)を保つための重要なカギであることがわかりました。
この発見は、量子の振る舞いを理解するうえでとても意義深いだけでなく、将来の技術にもつながる可能性があります。
たとえば、量子シミュレータや量子コンピュータでは、不要な熱の発生や量子のまとまりが崩れる「デコヒーレンス」が大きな問題になります。
今回の研究によって、どんな条件で熱化が抑えられるのか、また、どの程度の乱れまでなら耐えられるのかといった情報が得られれば、こうした機器の設計や改良のための重要なヒントになると考えられています。
今後の課題としては、さらに相互作用を強めたり、外から加える乱れの種類や大きさを変えたりして、局在状態がどこまで耐えられるかを調べることが挙げられます。
これにより、「熱化をどうコントロールできるか」を考えるうえでの、より実用的な設計指針が生まれるかもしれません。
そしてそれは、量子の世界のルールを深く理解し、未来の量子技術をより確かなものにしていくための大きな一歩となるでしょう。
元論文
Observation of many-body dynamical localization
https://doi.org/10.1126/science.adn8625
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


