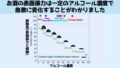ADHD(注意欠如・多動症)と診断される人は、子どもで約5%、大人で2.5%にのぼります。
ADHDは大人になるまで症状が発覚しないケースもあり、環境によりその症状の強弱は異なってきますが、基本的には遺伝が影響する先天的な症状だとされています。
しかし、「親や兄妹にはADHDの傾向がないのに、自分(または子ども)だけADHDだ」という人も存在します。
この“ちぐはぐさ”が、ADHDの遺伝をめぐる議論を長年分かりにくいものにしてきました。
そうなる原因は、ADHDには多数の遺伝子変異が複雑に関係しており、特定の遺伝子変異だけでADHDになる、というほど明確なものではないためです。
けれどデンマークのオーフス大学(Aarhus University)と米国ブロード研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)の国際研究チームが報告した新たな研究は、3つの遺伝子のいずれかに特定の変異があるだけでADHDの発症リスクが最大15倍まで高まることを突き止めました。
この発見は、特定の遺伝子においては、その変異がADHDの発症に大きな影響を与えうることを示しています。
この研究の詳細は、2025年11月12日付けで科学雑誌『Nature』に掲載された論文にまとめられています。
目次
- 遺伝の謎に迫るADHD研究の最前線
- なぜ「3つの遺伝子」がADHDと関係すると言えるのか
遺伝の謎に迫るADHD研究の最前線
ADHDは、子どものおよそ5%、大人では2.5%が持つ発達特性です。
家族内で似た傾向が見られることから、遺伝の影響は強いと考えられてきましたが、「どの遺伝子が、どのくらい関わるのか」という核心部分は長い間わからないままでした。
その謎を解きほぐそうと、デンマークとアメリカの研究チームは、ADHDと診断された8,895人の遺伝子を調べるという大規模調査に踏み切りました。
研究者たちが注目したのは、人の体をつくる設計図のうち、「エクソン(exon)」と呼ばれるタンパク質をつくる部分です。
ここには、体や脳の働きを直接左右する重要な情報が詰まっています。
研究チームは、数十万以上もある遺伝情報の中から、“まれだけれどもADHDの発症に影響が大きい”変化を徹底的に探し出しました。
その結果、ADHDのリスクを強く押し上げる3つの遺伝子が浮かび上がってきたのです。
ひとつめはMAP1A(Microtubule-Associated Protein 1A)で、神経細胞の形を支える“骨組み”をつくる働きがある遺伝子です。
ふたつめはANO8(Anoctamin 8)で、細胞の外と内でカルシウムイオンの流れを調節する仕組みに関わります。
みっつめはANK2(Ankyrin-B)で、神経が電気信号をスムーズに伝えるための足場を整える役割を担っています。
これらの遺伝子に“タンパク質の形が崩れるような変異”があると、ADHDの発症リスクは5倍から最大15倍にまで高まることがわかりました。
従来の研究では、1つの遺伝子がここまで大きな影響を持つケースはほとんど知られていなかったため、この発見はADHD研究にとって非常に重要な前進です。
さらに興味深いことに、こうした変異を持つADHDの人々は、初等教育のみで学校を終える割合が高かったり、長期の失業や低所得といった社会的な困難を抱えやすい傾向も確認されました。
今回の研究が見せてくれたのは、「ADHDとは単なる“集中力の問題”ではなく、脳を支える遺伝子の仕組みと深く結びついた特性である」という点です。
ただし、見つかった3つの遺伝子だけですべてが説明できるわけではありません。
むしろ、ここから先にこそ、この研究の面白さがあります。
なぜ「3つの遺伝子」がADHDと関係すると言えるのか
今回の研究で見つかった3つの遺伝子、MAP1A、ANO8、ANK2が本当にADHDと関係しているのか。
この結論には、かなり明確な結果が示されていました。
まず、研究チームはADHDと診断された8,895人と、診断のない53,780人を比較しました。
その結果、この3つの遺伝子には、タンパク質を壊してしまうほどの強い変異が、ADHDの人に偏って存在していることがわかったのです。
まれな変異であっても、ADHD側に集中していれば、病気の発症に関わっている可能性が非常に高くなります。
さらに、この3つの遺伝子がどんな仲間と一緒に働いているのか、いわゆる“遺伝子ネットワーク”を調べたところ、興味深い共通点が見えてきました。
MAP1Aは神経細胞の形づくり、ANO8とANK2は細胞内外のイオンの流れや電気信号の調整に関わっています。
これらを起点に広がる遺伝子ネットワークは、神経どうしがつながる「シナプス」、神経細胞の形を維持する「骨組み」、電気信号のやりとりを支える仕組みといった、脳の動きを支える中心的な働きと強く結びついていました。
そして極めて重要なのは、こうした遺伝子の集まりが、ドーパミン神経やGABA神経など、ADHDとの関連が以前から指摘されてきた神経細胞と一緒に働いていた点です。
ドーパミンは意欲や注意に関わり、GABAは脳の興奮を落ち着かせるブレーキ役です。
ADHD治療薬が関わると考えられてきたドーパミンなどの経路とも方向性が合っており、「行動の問題ではなく、神経ネットワークのバランスの問題である」という見方を後押しする結果になっています。
こうした複数の証拠が重なったことで、3つの遺伝子がADHDに関わる“確度の高い候補”として浮かび上がったのです。
“遺伝子だけでは説明できない”ことも忘れてはいけない
ただし、この発見は「ADHDはこの3つで決まる」という話ではありません。
依然として、ADHDは非常に多様な遺伝的原因を持つ特性であることは変わりません。
まず、今回見つかった3つの遺伝子を含む、「ごくまれだが強い影響を持つ変異」は、ADHDの人のうちおよそ2割に見つかったに過ぎません。
つまり、残りの多くの人は、別の要因によってADHDを発症している可能性があります。
多くの人では、数え切れないほどたくさんの「ごく小さな影響を持つ遺伝子変化」が少しずつ重なり合うことで、リスクが形作られていると考えられています。
ADHDが“多因子”と呼ばれるのは、このように発症の背景が一つではないためです。
そのため、今回のような「ごくまれだが強い影響を持つ変異」は、ADHD全体の遺伝的リスクのごく一部しか説明しません。
とはいえ、今回の結果が特別なのは、1つの遺伝子の変異としては極めて珍しいほど強い影響力が示されたことです。
ADHDの研究では、多くの遺伝子は「わずかにリスクを押し上げる程度」で、発症の確率を1.1倍や1.2倍にする“ごく小さな効果の積み重ね”が一般的とされています。
精神医学の遺伝学全体を見ても、オッズ比(リスク倍率)が2〜3であれば「強い影響」とされる世界です。
その中で今回の3遺伝子は、変異が1つあるだけで発症リスクが5〜15倍に跳ね上がるという、ほとんど例のない強さを示しました。(発症リスクの大きさはそれぞれ異なり、MAP1Aは約13倍、ANO8は約15倍、ANK2は約5倍 )
こうした“単独で強い効果を持つ遺伝子”が見つかること自体、ADHD研究では非常に新しい発見と言えます。
さらに研究チームは、「まれで強い変異」と、「たくさんの小さな変異の積み重ね(ポリジェニックリスク)」の両方を同時に調べました。
その結果、どちらが決定的というわけではなく、こうした遺伝的要因が足し算のように合わさってADHDのリスクを押し上げていることがわかったと述べています。
もちろん、同じ変異を持っていてもADHDを発症しない人も存在します。これはADHDが単に遺伝子変異だけの問題ではなく、環境や経験、そして脳の可塑性(柔軟に変化する力)も大きな役割を果たしているためだと考えられます。
今回の研究で得られた成果は非常に大きい一方で、限界も存在します。
解析の対象となったのは、主にデンマークを中心とする欧州系の人々のデータです。
異なる民族集団でも同じ遺伝子が同じ影響を持つかどうかは、これから明らかにしていく必要があります。
また、今回注目された“まれな変異”は、その名の通り数が少ないため、それぞれがどのように働くのかを細かく調べるには、さらに大規模な研究が必要です。
さらに、学歴や所得との関連は“関連がある”と示された段階で、「遺伝子がこうした結果を直接引き起こした」という因果関係までは証明できていません。
この研究は、ADHDの理解を一歩進める材料を提供してくれました。
たとえば、ADHDの中にも遺伝的な背景の違いによって“サブタイプ”があるのではないか、といった新しい分類が生まれる可能性があります。
また、ドーパミン神経とGABA神経の両方が関係していることが示されたことで、将来的にはそれぞれの神経回路に合わせた、新しい治療アプローチが生まれるかもしれません。
元論文
Rare genetic variants confer a high risk of ADHD and implicate neuronal biology
https://doi.org/10.1038/s41586-025-09702-8
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部